2010年04月30日
今日のまかない
お陰さまで、本日も
「モチ鰹」は完売しました。
残念ながら、鯛とアジは、残ってしまいました。
今日も、この「もち鰹」は、絶賛頂きました。
今日もまかないはツッチー作です。

明日は、久々の予約で満席です。
頑張ります!
「モチ鰹」は完売しました。
残念ながら、鯛とアジは、残ってしまいました。
今日も、この「もち鰹」は、絶賛頂きました。
今日もまかないはツッチー作です。

明日は、久々の予約で満席です。
頑張ります!
2010年04月30日
2010年04月30日
2010年04月30日
手ごたえあり!

昨日、森仁水産さんから頂いた「もち鰹」は、
お陰さまで完売しました。
この魚を食べて欲しくて、何名かの常連様に電話をしておきました。
2組のお客様が、僕の到着時刻に合わせてきてくれました。

5時25分に到着して、5時40分ぐらいには、
I君が綺麗に盛り付けてくれました。

最初のお客様
「おっ!これは違うな」
「おまんの言うとおり、モチモチしてる」
「これは、食べたことなかったなぁ」
と言う言葉を聞いて
ほっと安心しました。
その日、来られた全てのお客様に
「もち鰹」について説明をさせて頂くと、
その全てのお客様から、ご注文を頂きました。
残念ながら、後半のお客様には、完売して
お出しすることができませんでした。
そして、その全てのお客様から
「おいしい!」
「モチモチしている!」
「臭みが全くない」
とお褒めの言葉を頂きました。
また、調理場のI君も
鰹をさばく際に
「おっーー!包丁にまとわりつく」とちょっとした
感動の声が!
僕も試食用に切り身にしましたが、
鰹を切る感覚ではなく、粋のいいカンパチや〆たてのはまちを
切っている感覚でした。
今日も買い付けに行きたいと思っています。
いい魚を仕入れて、分けてくれた森仁水産さん
調理してくれたスタッフさん
そして、それを食べてくれたお客様
全てに感謝いたします。
みなさんのお陰で
僕は、人様のお役に立てたという
喜びを感じることが出来ました。
2010年04月29日
2010年04月29日
2010年04月29日
食べたことありますか?
「もち鰹」って、食べたことありますか?
モチ鰹と呼ばれ餅のように歯にまとわりつく独特の食感で
鰹は、本来かなり沖合で漁獲されますが、
春のこの時期はかなり陸地に近づいてきます。
漁港から遠くないところで獲れた鰹は、その日の内に死後硬直せずぷりぷりとしたまま運ばれて来ます。
昔は、この辰が浜でもあったそうですが
今は少なく、御坊で今あがっているらしいので
利益度外視で
高速飛ばして
今から、仕入にいってきます。
その美味しさが食べられるのは、
ほんの数時間です。
ぜひ、本日お越しください。
今まで食べたことない
鰹が食べられるはずです。
モチ鰹と呼ばれ餅のように歯にまとわりつく独特の食感で
鰹は、本来かなり沖合で漁獲されますが、
春のこの時期はかなり陸地に近づいてきます。
漁港から遠くないところで獲れた鰹は、その日の内に死後硬直せずぷりぷりとしたまま運ばれて来ます。
昔は、この辰が浜でもあったそうですが
今は少なく、御坊で今あがっているらしいので
利益度外視で
高速飛ばして
今から、仕入にいってきます。
その美味しさが食べられるのは、
ほんの数時間です。
ぜひ、本日お越しください。
今まで食べたことない
鰹が食べられるはずです。
2010年04月29日
第9条 新しい発明発見に努めよ
愉快に働く10か条
「第9条 新しい発明発見に努めよ」
これは、守・破・離の
「破」にあたるのでしょうか。
これまでにも、書かせて頂きましたが、
楽しく仕事をするためには
人から言われたことだけを
ただ、作業的にこなしていては
いけません。
どうすれば、もっと効率よくできるのか?
どうすれば、もっとお客様が喜ぶのか?
どうすれば、もっと他のスタッフたちが楽になるのか?
どうすれば、品質をよくできるのか?
など、仕事の改善を常に考える。
そして、新しいことにチャレンジし
新しいスキルや能力を身につけていく。
現在、いくつかの会社では
社員さんからの提案をいれる
ご意見箱をつくり、採用されると
それに対して、金一封がでるような
仕組みをつくっているそうです。
トヨタ自動車では、その数が
年間、何万とか何十万とかという数の
提案がなされるそうです。
一番お客様や、製品の近くで働くのは
一般社員さんです。
いい商品をつくり、お客様に喜んで
頂くことが会社の第1義であるなら
現場の社員さんからの顧客目線の
改善・提案が一番的確だと思います。
「第9条 新しい発明発見に努めよ」とは
「常に失敗を恐れず新しいことにチャレンジし
仕事に創意工夫をせよ」
ということだと、僕は思いました。
いよいよこのシリーズも残り1回となりました。
「第9条 新しい発明発見に努めよ」
これは、守・破・離の
「破」にあたるのでしょうか。
これまでにも、書かせて頂きましたが、
楽しく仕事をするためには
人から言われたことだけを
ただ、作業的にこなしていては
いけません。
どうすれば、もっと効率よくできるのか?
どうすれば、もっとお客様が喜ぶのか?
どうすれば、もっと他のスタッフたちが楽になるのか?
どうすれば、品質をよくできるのか?
など、仕事の改善を常に考える。
そして、新しいことにチャレンジし
新しいスキルや能力を身につけていく。
現在、いくつかの会社では
社員さんからの提案をいれる
ご意見箱をつくり、採用されると
それに対して、金一封がでるような
仕組みをつくっているそうです。
トヨタ自動車では、その数が
年間、何万とか何十万とかという数の
提案がなされるそうです。
一番お客様や、製品の近くで働くのは
一般社員さんです。
いい商品をつくり、お客様に喜んで
頂くことが会社の第1義であるなら
現場の社員さんからの顧客目線の
改善・提案が一番的確だと思います。
「第9条 新しい発明発見に努めよ」とは
「常に失敗を恐れず新しいことにチャレンジし
仕事に創意工夫をせよ」
ということだと、僕は思いました。
いよいよこのシリーズも残り1回となりました。
2010年04月28日
幸華2-単品メニュ編
2010年04月28日
いい体験

先日、串揚専門店で、同じIKORAブロガーの「幸華」さんへ行ってきました。
改装をされたばかりのようで、
店内は、とてもお洒落できれいなお店でした。

そして、私たちは、個室に通して頂きました。
床の間にも綺麗なライティングで飾られた花があり、心を癒してくれます。
 お料理は、串揚げをメインとして、
お料理は、串揚げをメインとして、豊富なメニューがありました。
 串揚げは、テーブルで自分で衣をつけて
串揚げは、テーブルで自分で衣をつけて揚げる、スタイルとなっていました。
右からミックス粉、とき粉、パン粉です。

私たちは、串揚げ18本盛合せを注文しました。
商品ごとに、揚げる時間や、どういう衣がいいかなどが書いた表があり
 それを見ながら、
それを見ながら、「あーでもない、こーでもない」と
楽しく揚げました。
そのほかにも一品料理を注文しましたが
続きは、また後ほど・・・
2010年04月27日
もう限界!

最近、動画の編集を行っているのですが、
付属のムービーメーカーでは、思うような効果や編集が出来ずに、
Adobe premierやVideo Studio を購入したのですが、
パソコンが殆ど、動かない!
何時間もかけて、編集しても、保存ができない。

そこで、2台あるパソコンを思い切って、1台に合体!
空いているメモリソケットに512mb×2枚を挿入!
 ハードディスクのシステムを削除して、2台にし
ハードディスクのシステムを削除して、2台にしセカンダリディスクにドキュメントファイルを移し
プライマリディスクの空き容量を増やす。

少し、早くなったような気がした。

祈るような気持ちで
Adobe premierを起動、編集に!
やっぱり、駄目でした。
クワッドコアが主流の時代に
シングルプロセッサーでは
動画編集は限界か!!!
i7だと、格段に早いと、友達に聞いたけど
自作でも、20万近くかかりそう!
しかも、Windows7の64bitにして、
システムディスクをSSDにすると
起動は秒速だときくけど、
現在僕の持っている32bitiのアプリケーションは、
果たして、動くのだろうか?
今日は、料理にも経営にも
まったく関係ない日記でした。
2010年04月26日
第8条 先輩の言行に学べ
愉快に働く10か条
「第8条 先輩の言行に学べ」
「我以外皆師」
私の好きな言葉です。
昔は、先輩や親の言うことを
まともに聞かないこともよくありましたが
年を重ねていろんな事がわかっていくうちに、
人生の先輩やその仕事の先輩
そして、先人の仰ることが、いかに正しいのか
また、人間というのは、多少の違いこそあれ
同じようなことで、壁にぶつかったり、間違いを犯し、
悩み、考えて生きているものだということが
少しづつわかってきました。
とは言っても、
人間には、長所、短所があるので、
全てが正しいわけでは、ないかもしれません。
しかし、それが正しいかどうかを決めているのが
もし、自分自身であるとしたら、
そのものさしが間違っているとしたら、どうでしょう?
必ずしも、その人の言行が間違っているとはいえないのではないでしょうか?
「守破離」という教えが武道にありますが、
これは、
守・・・師の教えを正しく真似て、覚える
破・・・教えられたことに工夫を加えて、それを超える
離・・・師から離れて、新しい境地に立つ。
簡単にいうとこんなことです。
つまり、仕事を進める上で、
まず、その道を通ってきた、先人の言行を真似てみるというのが
うまくいくコツであるということだと思います。
これとは、逆に
「あの上司の考え方は、おかしい」
「あの人の下では、働けない」
こんなことを考えていては、
それは、不平不満、愚痴ばかりとなり
仕事が楽しくなるはずがありません。
また、松下幸之助翁もピーター・ドラッガー博士も
人の長所を生かす経営をしなさいと
おっしゃっています。
「第8条 先輩の言行に学べ」とは
自分以外の人は、全てお手本だと思い、
真似て、学びなさい
ということだと、私は理解しました。
「第8条 先輩の言行に学べ」
「我以外皆師」
私の好きな言葉です。
昔は、先輩や親の言うことを
まともに聞かないこともよくありましたが
年を重ねていろんな事がわかっていくうちに、
人生の先輩やその仕事の先輩
そして、先人の仰ることが、いかに正しいのか
また、人間というのは、多少の違いこそあれ
同じようなことで、壁にぶつかったり、間違いを犯し、
悩み、考えて生きているものだということが
少しづつわかってきました。
とは言っても、
人間には、長所、短所があるので、
全てが正しいわけでは、ないかもしれません。
しかし、それが正しいかどうかを決めているのが
もし、自分自身であるとしたら、
そのものさしが間違っているとしたら、どうでしょう?
必ずしも、その人の言行が間違っているとはいえないのではないでしょうか?
「守破離」という教えが武道にありますが、
これは、
守・・・師の教えを正しく真似て、覚える
破・・・教えられたことに工夫を加えて、それを超える
離・・・師から離れて、新しい境地に立つ。
簡単にいうとこんなことです。
つまり、仕事を進める上で、
まず、その道を通ってきた、先人の言行を真似てみるというのが
うまくいくコツであるということだと思います。
これとは、逆に
「あの上司の考え方は、おかしい」
「あの人の下では、働けない」
こんなことを考えていては、
それは、不平不満、愚痴ばかりとなり
仕事が楽しくなるはずがありません。
また、松下幸之助翁もピーター・ドラッガー博士も
人の長所を生かす経営をしなさいと
おっしゃっています。
「第8条 先輩の言行に学べ」とは
自分以外の人は、全てお手本だと思い、
真似て、学びなさい
ということだと、私は理解しました。
2010年04月26日
豪華ランチ


今日は、連休中にお休みがとれないので、
休みを振り替えて、お休みとさせて頂きました。
月曜日は、山小屋さんも休みなので、
ご自宅で、お昼ごはんをごちそうになりました。
行ってみると、めちゃ豪華です。
お刺身に、ステーキ、ヒラマサかま塩焼き、
卵焼き、冷奴、わらびの炊いたん。
そして、僕の好きな納豆。
お腹いっぱいです。
こんなお昼ご飯を頂き、
とても幸せな時間でした。
2010年04月25日
特注プリン
2010年04月24日
2010年04月23日
撃沈
今日は、カップリングパーティーの日でした
多数の参加頂きまして、ありがとうございました
しかし、今回は、反省すべき点も多く、自分の無力さを痛感した日でした
次回までに、改善策を熟考したいと思います。

多数の参加頂きまして、ありがとうございました

しかし、今回は、反省すべき点も多く、自分の無力さを痛感した日でした

次回までに、改善策を熟考したいと思います。
2010年04月22日
今日のまかない

今日のまかないは、ツッチーが作ってくれた
ミックスフライ定食。
美味しかった。
メンチカツの作りかた
材料
牛ミンチまたは合挽きミンチ(牛7:豚3) 430g
玉ねぎ(小) 1個
パン粉 大さじ 3杯
牛乳 大さじ 1杯
塩 小さじ 1杯
こしょう 小さじ 1杯
ナツメグ 少々
ケッチャップ 大さじ 1杯
赤ワイン 大さじ 0.5
たまり 大さじ 0.5
作りかた
1、玉ねぎの食感を楽しみたい方は、生のままで。
そうでない方は、
みじん切りにした玉ねぎを炒め粗熱をとっておきます。
2、パン粉は牛乳で湿らせておきます。
3、全部の材料を混ぜる。
4、ハンバーグを作る要領で、空気を入れながら
50g〰60gにまとめる
5、小麦粉、溶き玉子、パン粉をつけて1701度から180.度の油でひっくりかえしながら5分から6分揚げる。
2010年04月22日
点と点が線になった。

この本の中で、一番最初に主人公が考えるのは
ピーター・ドラッガー博士の言葉
「自らの事業は、何かを知ることである」さらに、
自らの事業は何かを知ることほど、簡単でわかりきったことはないかに思われる。鉄鋼会社は鉄をつくり、鉄道会社は貨物と乗客を運び、損害保険会社は火災のリスクを引き受け、銀行は金を貸す。しかし実際には、われわれの事業は何かとの問いは、ほとんど常に答えることの難しい問いである。正解は決して明らかではない。
事業は、社名や定款や設立趣意書によって定義されるのではない。顧客が満足させる欲求によって定義される。顧客を満足させることが、企業の使命であり目的である。
「顧客は誰か。
これが最初に考えるべき問いである。」
顧客は誰かの問いこそ、企業の目的と使命を定義するうえで、
最初に考えるべき最も重要な問いである。
やさしい問いではない。
まして答えのわかりきった問いではない。
だが、この問いに対する答えによって、企業が自らを
どう定義するかが決まってくる。
この顧客は、誰かというのをこの本で考えているのですが、
その答えを見たときに、
僕の今まで、バラバラになっていたものが
ひとつなりました。
経営理念の大切さは、いろんな書物で説かれていますが、
ほとんどの経営理念の中には、社員さんたちに対する理念があります。
もちろん、私にもあります。
事業の目的と使命が顧客満足に応えることであるならば
経営理念は、顧客に対する想いであると思います。
そして、経営理念の中に、従業員さんに対する理念があるとするならば、
従業員さん=顧客である。
といえるのである。
最近は、この従業員満足(ES)の重要性が説かれ
サウスウエスト航空では、「ESがCSより第一義である」と名言しています。
僕は、従業員さんに対する理念と顧客に対する理念を別々に考えていました。
また、そうせざるを得ないと思っていました。
しかし、
従業員さん=顧客
と考えると、理念がよりスマートになります。
例えば、「顧客に感動を与える」と「従業員さんに感動をもって働く」という二つの理念は
「感動を生む会社」あるいは「感動を与える会社」でいいわけです。
この気づきを元にもう一度、経営理念を練り上げたいと思いました。
2010年04月21日
第7条 時々必ず大息を抜け
愉快に働く10か条
「第7条 時々必ず大息を抜け」
これは、文字通り、たまには
仕事の事を一切忘れ、リフレッシュをしなさいということです。
僕は、この中の『大息』ということばに注目しました。
深呼吸をする時に、たくさんの空気を吐き出そうと思えば、
たくさんの空気を吸わなければなりません。
つまり、大息を抜くためには、
仕事も全力でしなければいけません。
例えば、冬の寒い日に外で歩いたり、仕事をしたりしたとします。
体は、冷え切っています。
そんな時に、家に帰り、暖かいお風呂に入ったとき
僕は、とても幸せを感じます。
また、お店が忙しく、仕事を一生懸命したあとに食べるごはんは
とても美味しく、幸せを感じます。
逆に・・・
暖かい部屋にいて、ぬるま湯のお風呂に入っても、上記ほどの幸せ感や安堵感は感じられません。
また、なんとなく仕事をし終えた後の休息は、なんとなくけだるいものです。
「大息を抜け!」とは精神や体の緩急をつけなさいということだと僕は思いました。
また、大息を抜くことで、行き詰っていた仕事に新しいヒラメキが生まれます。
仕事をし続けると、頭の中がいっぱいになり、思考は停止するように
仕事が捗らなくなるときがあります。
そんな時に、全てを忘れ、大息を抜いてリフレッシュし、頭を空っぽにすることで
また、新しいヒラメキが生まれ、仕事が一気に進む時があります。
「時々必ず大息を抜け」とは
全力で仕事をして、そして全力で休息をする。
自分の時間の中で、緩急をつけなさい
ということだと思いました。
「第7条 時々必ず大息を抜け」
これは、文字通り、たまには
仕事の事を一切忘れ、リフレッシュをしなさいということです。
僕は、この中の『大息』ということばに注目しました。
深呼吸をする時に、たくさんの空気を吐き出そうと思えば、
たくさんの空気を吸わなければなりません。
つまり、大息を抜くためには、
仕事も全力でしなければいけません。
例えば、冬の寒い日に外で歩いたり、仕事をしたりしたとします。
体は、冷え切っています。
そんな時に、家に帰り、暖かいお風呂に入ったとき
僕は、とても幸せを感じます。
また、お店が忙しく、仕事を一生懸命したあとに食べるごはんは
とても美味しく、幸せを感じます。
逆に・・・
暖かい部屋にいて、ぬるま湯のお風呂に入っても、上記ほどの幸せ感や安堵感は感じられません。
また、なんとなく仕事をし終えた後の休息は、なんとなくけだるいものです。
「大息を抜け!」とは精神や体の緩急をつけなさいということだと僕は思いました。
また、大息を抜くことで、行き詰っていた仕事に新しいヒラメキが生まれます。
仕事をし続けると、頭の中がいっぱいになり、思考は停止するように
仕事が捗らなくなるときがあります。
そんな時に、全てを忘れ、大息を抜いてリフレッシュし、頭を空っぽにすることで
また、新しいヒラメキが生まれ、仕事が一気に進む時があります。
「時々必ず大息を抜け」とは
全力で仕事をして、そして全力で休息をする。
自分の時間の中で、緩急をつけなさい
ということだと思いました。
2010年04月20日
感動!涙!

先日、買ったこの本。
予想以上に素晴らしかった。
ドラッガーの本は、難解で、何冊も持っていますが、
どれも、読破していません。
そして、読んでいてもその内容が、深く理解できませんでした。
しかし、この本は、
高校野球の女子マネージャーのみなみちゃんと野球部の仲間たちが甲子園を目指して奮闘していく青春ドラマになっていて、とてもおもしろく、ドラッガーの言葉をみなみちゃんをはじめとする野球部のナインがどう理解し、どう考え、具体的にどう行動したのかが書かれているので、ものすごく理解しやすかったです。
そして、ドラマ(小説)としても、エンターテイメント性も高く、
最後の方では、感動で、思わず涙があふれてきました。
エンターテイメント性が高いのは、それもそのはずで
作者は、大学卒業後、作詞家の秋元康氏に師事。
放送作家として「とんねるずのみなさんのおかげです」「ダウンタウンのごっつええ感じ」等のテレビ番組の制作に参加。アイドルグループ「AKB48」のプロデュース等にも携わるという経歴の持ち主だそうです。
それだけに、272ページの本でしたが、2時間程度で読むことができるぐらい面白く理解しやすい本です。
組織とは、マネジメントとは、何か?
組織を活性化させるには、どうすればいいのかということがかわりやすく書かれていますので、
経営者や経営幹部はもちろん、地域のコミュニュニティや学校、クラブ活動など、すべての組織のリーダーやマネージャー的な人には、おすすめの本です。







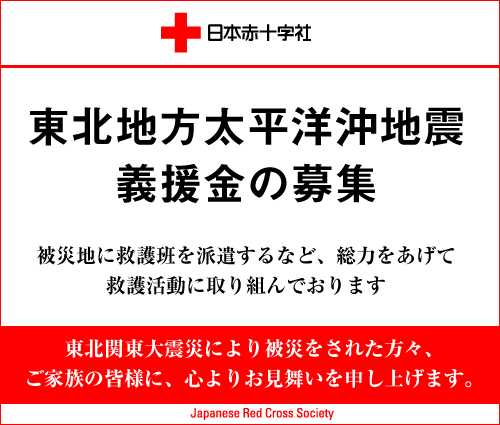


 今日も買いました。
今日も買いました。 















