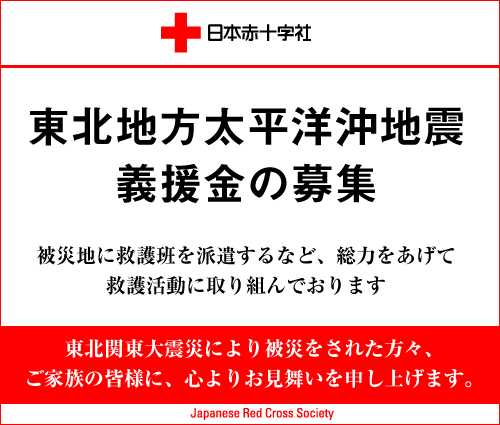2008年12月24日
僕のサンタクロース

今日は、予定がなかったので、一人でクリスマスイブを過ごそうと思っていましたが、
急きょ、お友達から、お誘いを頂き、一緒にごはんを食べて、そしてクリスマスケーキを食べました。
もうこの年で「ひとりでもいいかなぁ」って思っていたけど、なんとなく寂しい気持もあったので、
そんな僕の心を神様が見透かしたように、きっと僕にクリスマスプレゼントをくれたんだと思います。
そのお友達が、今年の僕のサンタクロースさんです。
サンタクロースってクリスマスイブの前夜にプレゼントを運んでくれる人というイメージがあります。
その由来は、wikipediaによると、
4世紀頃の東ローマ帝国小アジアの司教(主教)、キリスト教の教父聖ニコラオス(ニコラウス)の伝説が起源である。「ニコラオス」の名はギリシア語表記。ラテン語ではニコラウス。イタリア語、スペイン語、フランス語ではサン・ニコラ。イタリア語ではニコラオとも。ロシア語ではニコライ。
以下のような伝説のほか、右に挙げる絵画のように無実の罪に問われた死刑囚を救った聖伝も伝えられている。
「ある日ニコラウスは、貧しさのあまり、三人の娘を嫁がせることの出来ない家の存在を知った。ニコラウスは真夜中にその家を訪れ、屋根の上にある煙突から金貨を投げ入れる。このとき暖炉には靴下が下げられていたため、金貨は靴下の中に入っていたという。この金貨のおかげで娘の身売りを避けられた」という逸話が残されている。靴下の中にプレゼントを入れる風習も、ここから来ている。その後、1822年にニューヨークの神学者クレメント・クラーク・ムーア(コロンビア大学教授)が病身の子供のために作った詩「聖ニコラウスの訪問」がきっかけとなり、このサンタクロース物語は全米中に広まった(出典:「サンタクロースの大旅行」岩波新書80p)。
また、ニコラオスは学問の守護聖人として崇められており、アリウス異端と戦った偉大な教父でもあった。教会では聖人として列聖されているため、「聖(セント)ニコラオス」という呼称が使われる。これをオランダ語にすると「シンタクラース」である。オランダでは14世紀頃から聖ニコラウスの命日の12月6日を「シンタクラース祭」として祝う慣習があった。その後、17世紀アメリカに植民したオランダ人が「サンタクロース」と伝え、サンタクロースの語源になったようだ。
正教会系の国では、サンタクロースは厳密に「奇蹟者」の称号をもつ聖人たる聖ニコラオス(聖ニコライ)であり、聖ニコラオスの祭日は12月6日である(聖名祝日の項目を参照)。子供たちがこの日に枕元に靴下を吊るしておくと、翌朝に入っているのはお菓子である。クリスマスである12月25日は聖体礼儀に行く日で、プレゼントはない。
ユリウス暦を採用している正教会(エルサレム総主教庁、ロシア正教会など)の聖ニコラオスの祭日は12月19日であり、主の降誕祭(クリスマス)は、現行の暦に換算すると1月7日である(2008年現在、ユリウス暦とグレゴリオ暦の間には13日の差があるため)。ロシアでは1月7日にジェド・マロース(Дед мороз, マロース爺さん:マロースとはロシア語で「吹雪」「寒波」という意味)と孫のスニェグーロチカ(Снегурочка, 雪娘)がプレゼントを運んでくる。
また、トナカイは、8頭いるらしくて、それぞれに名前があるそうです。
ダッシャー (Dasher)
ダンサー (Dancer)
プランサー (Prancer)
ヴィクセン (Vixen)
ドゥンダー (Dunder)(後の版ではドンダー(Donder)となっている)
ブリッツェン (Blitzen)
キューピッド (Cupid)
コメット (Comet)
またさらに、9頭目の「赤鼻のトナカイ」の歌(原題:Rudolph the Red-Nosed Reindeer|Rudolph the Red-Nosed Reindeer )で有名なルドルフ (Rudolph) は1939年にロバート・メイ著の「真っ赤なお鼻のルドルフ」から8頭の先導役として先頭を走る1頭で足されている。
《引用終わり》
今は、経済が停滞し、不安定な世の中ですが、心だけは、夢をもって生きていきたいと思います。
今日も、幸せな1日に感謝です。