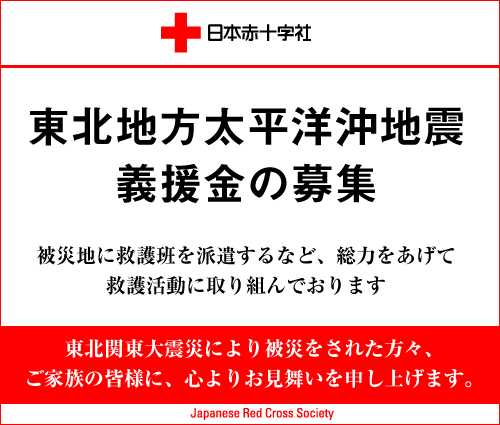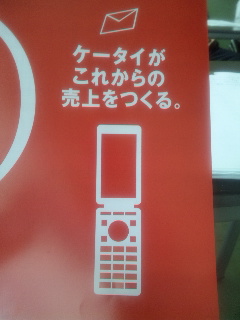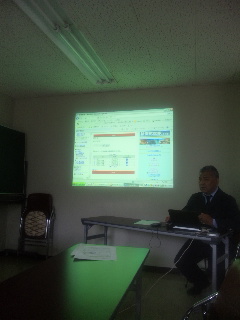2010年07月30日
山ごもり

箕面の滝です。
マイナスイオンがいっぱいでとても気持ちよかったです。
今日の朝に行ってきました。
といっても、観光ではありません。
昔参加させて頂いた研修の同窓会です。
8ヶ月間共にした仲間なので、久しぶりに会うと
話が盛り上がります。
そして、話の内容は
みんな経営の事や
お互いの業界の話です。
また、2名の仲間の経営発表や
田舞代表講師の特別講和もありました。

また、次のブログで所感を書きたいと思います。
2010年07月17日
絶対にモテる方法
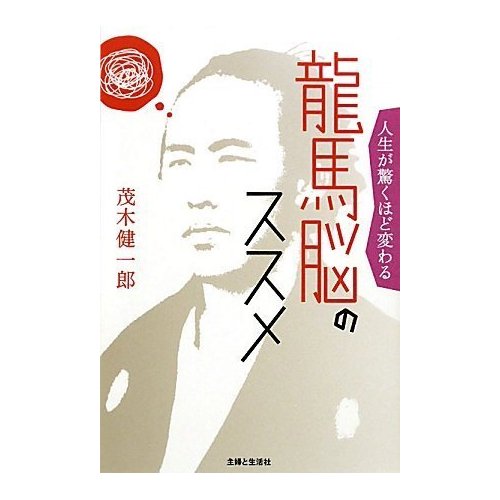
昨日の、歓迎会&お誕生日会は
お友達のお店 「みな月」に無理を言って
本来ならラストオーダーの時間の
00:30分に入店させて頂きました。
昨日は、スタッフ以外にも
たまたまお店に来てくれていた友達も同席してくれたので
写真をとるのを控えましたので、残念ながら写真はありませんが
どれも、美味しい料理とドリンクでした。
さて、タイトルとの「絶対にモテる方法!」
これは、僕が発見したのではなく
『龍馬脳のススメ』の中に書いてあったことですが
まさに昨日は、それを実感した場でした。
絶対にモテる方法とは
坂本龍馬さんのコミュニケーション能力について書かれている
一節ですが
その内容のポイントは
1、ダメダメ語り
2、ユーモア
3、下から目線
これは、作者の茂木健一郎さんと
龍馬伝で主役を演じる福山雅治さんの対談の中で
発見したポイントだそうです。
これは、脳科学的にも根拠があるそうですが
詳しくは、本をお読み頂くとして、
僕なりの解釈を書きます。
初めての人とコミュニケーションは、大なり小なり誰でも緊張します。
しかし、その出逢いを大切にして、相手の懐に入るのには
1回では、なかなか難しいものです。
しかし、龍馬は、その1回で相手の懐にぐっと入ったのです。
それは、自分の駄目な所や弱い所、恥ずかしい所を
ユーモアと笑いを交えて、話をする。
自分をさらけ出すオープンマインドで接してこられると
こちらも、気持ちが楽になります。
でも、多くの人は、初めてあった相手に少しでも
自分をよく見せようとしたり
相手より、自分の方が上の立場に立ちたがったりします。
まぁ、変なプライドっていうんですかね。
お笑い芸人さんは、
よく自分の欠点をネタに笑いをとりますよね。
だから、芸人さんってもてるんでしょうね。
そういう意味では、龍馬も芸人さんと言えるのかもしれません。
初めて人やあまり仲良くない人とコミュニケーションをとるコツは、
自分を必要以上に大きく見せようとせず、
相手より、へりくだり、自分の欠点を先にさらけ出すことが
大切だと思いました。
ちょっとまとまりのない文書すいません。
2010年07月01日
不思議な出来事
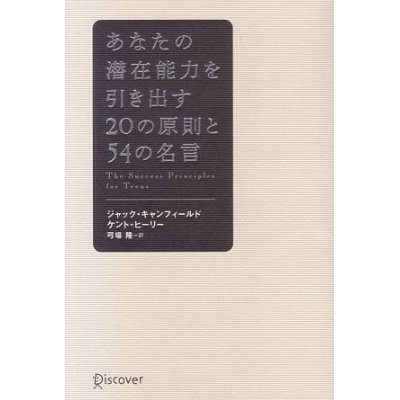
ネットサーフィンをしていて行き着いたこの本。
AMAZONでチェックすると結構人気の本。
ちょうど、新しい本を買おうと思っていたので
なんとなく買ってみた。
そして、今日届いた。

今日は、休みだったのですが
やりたいことがあったので
予定をいれずに空けておきました。
でも、やりたいことの半分も達成できず
ネガティブな気分になっていました。
ここ最近のストレス解消法は、走ること。
しかし、これも膝痛のため、ここ3週間は
走ることも出来ない。
そして、なんとなくこの本を開いてみると
びっくり!

簡単に言うと、「思考は現実化する」や「引き寄せの法則」に共通するように
自分の思考や口癖が今の現実を作っているという内容の本ですが、
最初のページの方に
自分のよくしている言葉を紙に書き出してみてくださいと書いてありました。
僕は、
ここ2、3日の自分の心のつぶやきや思考、独り言を紙に書き出してみました。
すると
見事にネガティブな言葉ばかりでした。
そこで、それらの言葉を二重線を引いて消して
全て、ポジティブな言葉に書き換えてみました。
すると
体が軽くなり、頭がすっきりしました。
やはり、人間の思考と体は繋がっているようです。
しかし、僕がタイトルで書いた
「不思議な出来事」とは
この事では、ありません。
この本を手にしたタイミングです。
この本を注文した時に
こういう感情に支配されてたわけではありません。
いや、もしかしたら
気がついていなかっただけなのかもしれませんが
いずれにしても、この本を注文する時点では
どうしても読みたい本では、なかったのですが
今日の僕の感情を予知していたかのように
今日、この本が届いたのです。
神様っているんですね。
もし、みなさんの中に
今、人生がうまくいかないと思っている方がいらっしゃいましたら
この本を、手にして見られては、いかがでしょうか?
2010年06月09日
成功の極意
先日の講習会で、『ハインリッヒの法則』を学びました。
この法則は、別に「ヒヤリ・ハットの法則」とも呼ばれ、
参考:wilipedia
この法則、1:29:300の法則は、災害だけでなく、
自社の商品の欠陥や、お客様のクレームにも当てはまるとして、
よく話しに出てきます。
この法則を導かれた対象がどれぐらいのデータから取ったかは分らないし、
他の科学的根拠もないので、数字の信憑性はともかく
大切なことは、
大きな失敗とは、それを予知するような小さい失敗を繰り返している。
ということです。
例えば、車の運転中に、ちょっと携帯電話やナビの操作をしていて
「ハッ」とした経験のある方は、わき見運転などで交通事故を起こす可能性があるということです。
飲食店でいうと、グラスをひっくり返して、お客様の服を汚してしまうとうような失敗を起こした人は、
普段でも、お盆の上で、グラスが傾いていたり、揺れたり、あるいは、バックヤードでひっくり返すというような
事を繰り返しているということです。
ですから
「小さいことだから、改善しなくてもいい。小さいことだから見過ごしてもいいという考え方は、大きな変革をあきらめる」ということに繋がると僕は思います。
二宮尊徳の言葉に「積小為大」という言葉があります。
また
イエローハットの鍵山秀三郎さんの言葉に「ひとつ拾えば、ひとつだけきれいになる」と言う言葉があります。
一攫千金を夢見る人がいますが、
日々の小さい改善が大きな結果を生むのです。
運よく、短期間に大きな成功を手にした人は、
早く衰退すると、僕は思います。
毎日の平凡でつまらないと思えるようなことでも
ひとつひとつを丁寧に行い、自分の技術を磨き
そして、考え
改善を繰り返していく。
そんな生き方ができればいいなぁと思います。
この法則は、別に「ヒヤリ・ハットの法則」とも呼ばれ、
これはアメリカの技師ハインリッヒが発表した法則で、
労働災害の事例の統計を分析した結果、導き出されたものです。
数字の意味は、
重大災害 1に対して
軽傷の事故 29
無傷災害は 300
になるというもので、
これをもとに
「1件の重大災害(死亡・重傷)が発生する背景に、29件の軽傷事故と300件のヒヤリ・ハットがある。」
という警告として、よく安全活動の中で出てくる言葉です。日常、ヒヤリ・ハットの状態にまでいかないが(もしくは自覚しない)、実は非常に不安全な状態や行為となると、相当な件数になるはずです。いつもやっていることだから、今までも平気だったので……、という不安全行為が、いつヒヤリ・ハットを飛び越え一気に重大災害になるかも知れません。「1:29:300」でいい表されている比率は、よく考えれば非常に高い確率で重大事故を招くことを示唆しています。いつやって来るか分からない災害を未然に防ぐには、不安全な状態や行為を認識し、ヒヤリ・ハットの段階で地道に対策を考え、実行(よい習慣として身につける)していくことが重要です。
参考:wilipedia
この法則、1:29:300の法則は、災害だけでなく、
自社の商品の欠陥や、お客様のクレームにも当てはまるとして、
よく話しに出てきます。
この法則を導かれた対象がどれぐらいのデータから取ったかは分らないし、
他の科学的根拠もないので、数字の信憑性はともかく
大切なことは、
大きな失敗とは、それを予知するような小さい失敗を繰り返している。
ということです。
例えば、車の運転中に、ちょっと携帯電話やナビの操作をしていて
「ハッ」とした経験のある方は、わき見運転などで交通事故を起こす可能性があるということです。
飲食店でいうと、グラスをひっくり返して、お客様の服を汚してしまうとうような失敗を起こした人は、
普段でも、お盆の上で、グラスが傾いていたり、揺れたり、あるいは、バックヤードでひっくり返すというような
事を繰り返しているということです。
ですから
「小さいことだから、改善しなくてもいい。小さいことだから見過ごしてもいいという考え方は、大きな変革をあきらめる」ということに繋がると僕は思います。
二宮尊徳の言葉に「積小為大」という言葉があります。
また
イエローハットの鍵山秀三郎さんの言葉に「ひとつ拾えば、ひとつだけきれいになる」と言う言葉があります。
一攫千金を夢見る人がいますが、
日々の小さい改善が大きな結果を生むのです。
運よく、短期間に大きな成功を手にした人は、
早く衰退すると、僕は思います。
毎日の平凡でつまらないと思えるようなことでも
ひとつひとつを丁寧に行い、自分の技術を磨き
そして、考え
改善を繰り返していく。
そんな生き方ができればいいなぁと思います。
2010年05月19日
2010年05月11日
第10条 仕事の報酬は仕事である
愉快に働く10か条
「第10条 仕事の報酬は仕事である」
今回でこのシリーズは、最終回となります。
そして、今までの文章は、
「〰せよ。」「思え!」などの命令形になっているのに
今回だけが、断定的な表現になっています。
ですから、これが最終章でもあるので
藤原銀次郎翁が一番言いたかったことであると
理解し、深く長く考えました。
だから、なかなか更新できなかったのですが、
結局行き着くところは、ひとつしかなく、
UPすることにしました。
報酬とは、本来労働に対する、給与や賃金を指します。
その労働に対する報酬がまた、労働であると言われると
どう解釈すべきなのかをずーっと考えていました。
そこで、第1条から第9条を読み返すと、
仕事とは、現状に満足せずに、常に研究を重ねて
よりレベルの高い仕事を追い求めなさい
と言ったことに集約されるように思いました。
そして、報酬をお金などではなく、得られるものと考えると
仕事の報酬=仕事を通じて、学び、自らの成長できること。
成長とは、ヒューマンスキルや専門的なテクニカルスキルやコンセプチュアルスキルなど
多岐にわたります。
そして
成長した自分=より、レベルの高い仕事に従事できる。任せられる。
よって
仕事の報酬=仕事
という三段論法が成立しました。
とすれば、仕事の意味や生きる意味というのは、
人間とは、仕事を通じて、(完成された)人間に近づいていく。
ということではないかと思いました。
結論として、
藤原銀次郎翁は、
「愉快に働く10か条」と題して
人生における仕事の重要性を説いたのだと理解しました。
「第10条 仕事の報酬は仕事である」
今回でこのシリーズは、最終回となります。
そして、今までの文章は、
「〰せよ。」「思え!」などの命令形になっているのに
今回だけが、断定的な表現になっています。
ですから、これが最終章でもあるので
藤原銀次郎翁が一番言いたかったことであると
理解し、深く長く考えました。
だから、なかなか更新できなかったのですが、
結局行き着くところは、ひとつしかなく、
UPすることにしました。
報酬とは、本来労働に対する、給与や賃金を指します。
その労働に対する報酬がまた、労働であると言われると
どう解釈すべきなのかをずーっと考えていました。
そこで、第1条から第9条を読み返すと、
仕事とは、現状に満足せずに、常に研究を重ねて
よりレベルの高い仕事を追い求めなさい
と言ったことに集約されるように思いました。
そして、報酬をお金などではなく、得られるものと考えると
仕事の報酬=仕事を通じて、学び、自らの成長できること。
成長とは、ヒューマンスキルや専門的なテクニカルスキルやコンセプチュアルスキルなど
多岐にわたります。
そして
成長した自分=より、レベルの高い仕事に従事できる。任せられる。
よって
仕事の報酬=仕事
という三段論法が成立しました。
とすれば、仕事の意味や生きる意味というのは、
人間とは、仕事を通じて、(完成された)人間に近づいていく。
ということではないかと思いました。
結論として、
藤原銀次郎翁は、
「愉快に働く10か条」と題して
人生における仕事の重要性を説いたのだと理解しました。
2010年04月29日
第9条 新しい発明発見に努めよ
愉快に働く10か条
「第9条 新しい発明発見に努めよ」
これは、守・破・離の
「破」にあたるのでしょうか。
これまでにも、書かせて頂きましたが、
楽しく仕事をするためには
人から言われたことだけを
ただ、作業的にこなしていては
いけません。
どうすれば、もっと効率よくできるのか?
どうすれば、もっとお客様が喜ぶのか?
どうすれば、もっと他のスタッフたちが楽になるのか?
どうすれば、品質をよくできるのか?
など、仕事の改善を常に考える。
そして、新しいことにチャレンジし
新しいスキルや能力を身につけていく。
現在、いくつかの会社では
社員さんからの提案をいれる
ご意見箱をつくり、採用されると
それに対して、金一封がでるような
仕組みをつくっているそうです。
トヨタ自動車では、その数が
年間、何万とか何十万とかという数の
提案がなされるそうです。
一番お客様や、製品の近くで働くのは
一般社員さんです。
いい商品をつくり、お客様に喜んで
頂くことが会社の第1義であるなら
現場の社員さんからの顧客目線の
改善・提案が一番的確だと思います。
「第9条 新しい発明発見に努めよ」とは
「常に失敗を恐れず新しいことにチャレンジし
仕事に創意工夫をせよ」
ということだと、僕は思いました。
いよいよこのシリーズも残り1回となりました。
「第9条 新しい発明発見に努めよ」
これは、守・破・離の
「破」にあたるのでしょうか。
これまでにも、書かせて頂きましたが、
楽しく仕事をするためには
人から言われたことだけを
ただ、作業的にこなしていては
いけません。
どうすれば、もっと効率よくできるのか?
どうすれば、もっとお客様が喜ぶのか?
どうすれば、もっと他のスタッフたちが楽になるのか?
どうすれば、品質をよくできるのか?
など、仕事の改善を常に考える。
そして、新しいことにチャレンジし
新しいスキルや能力を身につけていく。
現在、いくつかの会社では
社員さんからの提案をいれる
ご意見箱をつくり、採用されると
それに対して、金一封がでるような
仕組みをつくっているそうです。
トヨタ自動車では、その数が
年間、何万とか何十万とかという数の
提案がなされるそうです。
一番お客様や、製品の近くで働くのは
一般社員さんです。
いい商品をつくり、お客様に喜んで
頂くことが会社の第1義であるなら
現場の社員さんからの顧客目線の
改善・提案が一番的確だと思います。
「第9条 新しい発明発見に努めよ」とは
「常に失敗を恐れず新しいことにチャレンジし
仕事に創意工夫をせよ」
ということだと、僕は思いました。
いよいよこのシリーズも残り1回となりました。
2010年04月26日
第8条 先輩の言行に学べ
愉快に働く10か条
「第8条 先輩の言行に学べ」
「我以外皆師」
私の好きな言葉です。
昔は、先輩や親の言うことを
まともに聞かないこともよくありましたが
年を重ねていろんな事がわかっていくうちに、
人生の先輩やその仕事の先輩
そして、先人の仰ることが、いかに正しいのか
また、人間というのは、多少の違いこそあれ
同じようなことで、壁にぶつかったり、間違いを犯し、
悩み、考えて生きているものだということが
少しづつわかってきました。
とは言っても、
人間には、長所、短所があるので、
全てが正しいわけでは、ないかもしれません。
しかし、それが正しいかどうかを決めているのが
もし、自分自身であるとしたら、
そのものさしが間違っているとしたら、どうでしょう?
必ずしも、その人の言行が間違っているとはいえないのではないでしょうか?
「守破離」という教えが武道にありますが、
これは、
守・・・師の教えを正しく真似て、覚える
破・・・教えられたことに工夫を加えて、それを超える
離・・・師から離れて、新しい境地に立つ。
簡単にいうとこんなことです。
つまり、仕事を進める上で、
まず、その道を通ってきた、先人の言行を真似てみるというのが
うまくいくコツであるということだと思います。
これとは、逆に
「あの上司の考え方は、おかしい」
「あの人の下では、働けない」
こんなことを考えていては、
それは、不平不満、愚痴ばかりとなり
仕事が楽しくなるはずがありません。
また、松下幸之助翁もピーター・ドラッガー博士も
人の長所を生かす経営をしなさいと
おっしゃっています。
「第8条 先輩の言行に学べ」とは
自分以外の人は、全てお手本だと思い、
真似て、学びなさい
ということだと、私は理解しました。
「第8条 先輩の言行に学べ」
「我以外皆師」
私の好きな言葉です。
昔は、先輩や親の言うことを
まともに聞かないこともよくありましたが
年を重ねていろんな事がわかっていくうちに、
人生の先輩やその仕事の先輩
そして、先人の仰ることが、いかに正しいのか
また、人間というのは、多少の違いこそあれ
同じようなことで、壁にぶつかったり、間違いを犯し、
悩み、考えて生きているものだということが
少しづつわかってきました。
とは言っても、
人間には、長所、短所があるので、
全てが正しいわけでは、ないかもしれません。
しかし、それが正しいかどうかを決めているのが
もし、自分自身であるとしたら、
そのものさしが間違っているとしたら、どうでしょう?
必ずしも、その人の言行が間違っているとはいえないのではないでしょうか?
「守破離」という教えが武道にありますが、
これは、
守・・・師の教えを正しく真似て、覚える
破・・・教えられたことに工夫を加えて、それを超える
離・・・師から離れて、新しい境地に立つ。
簡単にいうとこんなことです。
つまり、仕事を進める上で、
まず、その道を通ってきた、先人の言行を真似てみるというのが
うまくいくコツであるということだと思います。
これとは、逆に
「あの上司の考え方は、おかしい」
「あの人の下では、働けない」
こんなことを考えていては、
それは、不平不満、愚痴ばかりとなり
仕事が楽しくなるはずがありません。
また、松下幸之助翁もピーター・ドラッガー博士も
人の長所を生かす経営をしなさいと
おっしゃっています。
「第8条 先輩の言行に学べ」とは
自分以外の人は、全てお手本だと思い、
真似て、学びなさい
ということだと、私は理解しました。
2010年04月22日
点と点が線になった。

この本の中で、一番最初に主人公が考えるのは
ピーター・ドラッガー博士の言葉
「自らの事業は、何かを知ることである」さらに、
自らの事業は何かを知ることほど、簡単でわかりきったことはないかに思われる。鉄鋼会社は鉄をつくり、鉄道会社は貨物と乗客を運び、損害保険会社は火災のリスクを引き受け、銀行は金を貸す。しかし実際には、われわれの事業は何かとの問いは、ほとんど常に答えることの難しい問いである。正解は決して明らかではない。
事業は、社名や定款や設立趣意書によって定義されるのではない。顧客が満足させる欲求によって定義される。顧客を満足させることが、企業の使命であり目的である。
「顧客は誰か。
これが最初に考えるべき問いである。」
顧客は誰かの問いこそ、企業の目的と使命を定義するうえで、
最初に考えるべき最も重要な問いである。
やさしい問いではない。
まして答えのわかりきった問いではない。
だが、この問いに対する答えによって、企業が自らを
どう定義するかが決まってくる。
この顧客は、誰かというのをこの本で考えているのですが、
その答えを見たときに、
僕の今まで、バラバラになっていたものが
ひとつなりました。
経営理念の大切さは、いろんな書物で説かれていますが、
ほとんどの経営理念の中には、社員さんたちに対する理念があります。
もちろん、私にもあります。
事業の目的と使命が顧客満足に応えることであるならば
経営理念は、顧客に対する想いであると思います。
そして、経営理念の中に、従業員さんに対する理念があるとするならば、
従業員さん=顧客である。
といえるのである。
最近は、この従業員満足(ES)の重要性が説かれ
サウスウエスト航空では、「ESがCSより第一義である」と名言しています。
僕は、従業員さんに対する理念と顧客に対する理念を別々に考えていました。
また、そうせざるを得ないと思っていました。
しかし、
従業員さん=顧客
と考えると、理念がよりスマートになります。
例えば、「顧客に感動を与える」と「従業員さんに感動をもって働く」という二つの理念は
「感動を生む会社」あるいは「感動を与える会社」でいいわけです。
この気づきを元にもう一度、経営理念を練り上げたいと思いました。
2010年04月21日
第7条 時々必ず大息を抜け
愉快に働く10か条
「第7条 時々必ず大息を抜け」
これは、文字通り、たまには
仕事の事を一切忘れ、リフレッシュをしなさいということです。
僕は、この中の『大息』ということばに注目しました。
深呼吸をする時に、たくさんの空気を吐き出そうと思えば、
たくさんの空気を吸わなければなりません。
つまり、大息を抜くためには、
仕事も全力でしなければいけません。
例えば、冬の寒い日に外で歩いたり、仕事をしたりしたとします。
体は、冷え切っています。
そんな時に、家に帰り、暖かいお風呂に入ったとき
僕は、とても幸せを感じます。
また、お店が忙しく、仕事を一生懸命したあとに食べるごはんは
とても美味しく、幸せを感じます。
逆に・・・
暖かい部屋にいて、ぬるま湯のお風呂に入っても、上記ほどの幸せ感や安堵感は感じられません。
また、なんとなく仕事をし終えた後の休息は、なんとなくけだるいものです。
「大息を抜け!」とは精神や体の緩急をつけなさいということだと僕は思いました。
また、大息を抜くことで、行き詰っていた仕事に新しいヒラメキが生まれます。
仕事をし続けると、頭の中がいっぱいになり、思考は停止するように
仕事が捗らなくなるときがあります。
そんな時に、全てを忘れ、大息を抜いてリフレッシュし、頭を空っぽにすることで
また、新しいヒラメキが生まれ、仕事が一気に進む時があります。
「時々必ず大息を抜け」とは
全力で仕事をして、そして全力で休息をする。
自分の時間の中で、緩急をつけなさい
ということだと思いました。
「第7条 時々必ず大息を抜け」
これは、文字通り、たまには
仕事の事を一切忘れ、リフレッシュをしなさいということです。
僕は、この中の『大息』ということばに注目しました。
深呼吸をする時に、たくさんの空気を吐き出そうと思えば、
たくさんの空気を吸わなければなりません。
つまり、大息を抜くためには、
仕事も全力でしなければいけません。
例えば、冬の寒い日に外で歩いたり、仕事をしたりしたとします。
体は、冷え切っています。
そんな時に、家に帰り、暖かいお風呂に入ったとき
僕は、とても幸せを感じます。
また、お店が忙しく、仕事を一生懸命したあとに食べるごはんは
とても美味しく、幸せを感じます。
逆に・・・
暖かい部屋にいて、ぬるま湯のお風呂に入っても、上記ほどの幸せ感や安堵感は感じられません。
また、なんとなく仕事をし終えた後の休息は、なんとなくけだるいものです。
「大息を抜け!」とは精神や体の緩急をつけなさいということだと僕は思いました。
また、大息を抜くことで、行き詰っていた仕事に新しいヒラメキが生まれます。
仕事をし続けると、頭の中がいっぱいになり、思考は停止するように
仕事が捗らなくなるときがあります。
そんな時に、全てを忘れ、大息を抜いてリフレッシュし、頭を空っぽにすることで
また、新しいヒラメキが生まれ、仕事が一気に進む時があります。
「時々必ず大息を抜け」とは
全力で仕事をして、そして全力で休息をする。
自分の時間の中で、緩急をつけなさい
ということだと思いました。
2010年04月20日
感動!涙!

先日、買ったこの本。
予想以上に素晴らしかった。
ドラッガーの本は、難解で、何冊も持っていますが、
どれも、読破していません。
そして、読んでいてもその内容が、深く理解できませんでした。
しかし、この本は、
高校野球の女子マネージャーのみなみちゃんと野球部の仲間たちが甲子園を目指して奮闘していく青春ドラマになっていて、とてもおもしろく、ドラッガーの言葉をみなみちゃんをはじめとする野球部のナインがどう理解し、どう考え、具体的にどう行動したのかが書かれているので、ものすごく理解しやすかったです。
そして、ドラマ(小説)としても、エンターテイメント性も高く、
最後の方では、感動で、思わず涙があふれてきました。
エンターテイメント性が高いのは、それもそのはずで
作者は、大学卒業後、作詞家の秋元康氏に師事。
放送作家として「とんねるずのみなさんのおかげです」「ダウンタウンのごっつええ感じ」等のテレビ番組の制作に参加。アイドルグループ「AKB48」のプロデュース等にも携わるという経歴の持ち主だそうです。
それだけに、272ページの本でしたが、2時間程度で読むことができるぐらい面白く理解しやすい本です。
組織とは、マネジメントとは、何か?
組織を活性化させるには、どうすればいいのかということがかわりやすく書かれていますので、
経営者や経営幹部はもちろん、地域のコミュニュニティや学校、クラブ活動など、すべての組織のリーダーやマネージャー的な人には、おすすめの本です。
2010年04月19日
第6条 仕事に使はれて人に使はれるな
愉快に働く10か条
「第6条 仕事に使はれて人に使はれるな」
私が初めて仕事をしたのは、
クラブ活動も卒業し、大学も決まった冬休みのことでした。
きっかけは、忘れましたが
京都駅観光デパート(現CUBE)の甘党の店で、バイトを始めました。
最初の頃は、言われたことだけをして、あとはぼっーと立っていることが多かったと思います。
そして、少し慣れてくると教えられたことだけをしていました。
教えられたことでも、他の誰かがしていると
手伝ったり、代わってすることもありませんでした。
お店を辞めるときに言われた
「返事だけよかったのを覚えておくよ」という
言葉だけが今でも心に残っています。
そして、大学に入った、最初の夏休み
今度は、新都ホテルの「四川」という中華料理屋で働きました。
ここでも、教えられたことしかしない。
それどころか、要領を覚え
サボることや、口ごたえをすることまで覚えて
タチが悪い。
今から思えば、恥ずかしい限りです。
でも、バイトは楽しかったんです。
何が楽しかったかと言うと
空いている時間に同じバイト仲間と
ペラペラとおしゃべりしたり
終わってから遊びに行ったり
まかないをお腹いっぱい食べさせてもらったり。
では、これが藤原銀次郎翁のおっしゃる「愉快に働く」ということなのか?
間違いなく違います。
僕が楽しいと感じてたことは、
遊びで得られる楽しさです。
決して、仕事で得られる楽しさではありません。
それでも、僕は仕事をしていると思っていましたが
それは、ただ、言われたこと、教えられたこと、お客様のいわれた事を
まるで、言葉のわかるロボットのようにこなしている作業でした。
仕事とは、自らが考えて、周りのスタッフと協力し、
お客様に喜ばれ具体的な成果をつくり、会社や世の中に貢献している」と実感し
そして、その過程で、自らが成長できたと実感できたときに楽しくなってくると
僕は、思います。
「人に使われるな」とは
「上司やお客様、同業者様などの他人から指示されて動く」
指示待ち人間ではダメだとおっしゃっているのです。
「仕事に使はれて人に使はれるな」とは
「他人に依存せず、自らが、主体的に、考え行動し、具体的な成果をつくること」
だと僕は解釈しました。
「第6条 仕事に使はれて人に使はれるな」
私が初めて仕事をしたのは、
クラブ活動も卒業し、大学も決まった冬休みのことでした。
きっかけは、忘れましたが
京都駅観光デパート(現CUBE)の甘党の店で、バイトを始めました。
最初の頃は、言われたことだけをして、あとはぼっーと立っていることが多かったと思います。
そして、少し慣れてくると教えられたことだけをしていました。
教えられたことでも、他の誰かがしていると
手伝ったり、代わってすることもありませんでした。
お店を辞めるときに言われた
「返事だけよかったのを覚えておくよ」という
言葉だけが今でも心に残っています。
そして、大学に入った、最初の夏休み
今度は、新都ホテルの「四川」という中華料理屋で働きました。
ここでも、教えられたことしかしない。
それどころか、要領を覚え
サボることや、口ごたえをすることまで覚えて
タチが悪い。
今から思えば、恥ずかしい限りです。
でも、バイトは楽しかったんです。
何が楽しかったかと言うと
空いている時間に同じバイト仲間と
ペラペラとおしゃべりしたり
終わってから遊びに行ったり
まかないをお腹いっぱい食べさせてもらったり。
では、これが藤原銀次郎翁のおっしゃる「愉快に働く」ということなのか?
間違いなく違います。
僕が楽しいと感じてたことは、
遊びで得られる楽しさです。
決して、仕事で得られる楽しさではありません。
それでも、僕は仕事をしていると思っていましたが
それは、ただ、言われたこと、教えられたこと、お客様のいわれた事を
まるで、言葉のわかるロボットのようにこなしている作業でした。
仕事とは、自らが考えて、周りのスタッフと協力し、
お客様に喜ばれ具体的な成果をつくり、会社や世の中に貢献している」と実感し
そして、その過程で、自らが成長できたと実感できたときに楽しくなってくると
僕は、思います。
「人に使われるな」とは
「上司やお客様、同業者様などの他人から指示されて動く」
指示待ち人間ではダメだとおっしゃっているのです。
「仕事に使はれて人に使はれるな」とは
「他人に依存せず、自らが、主体的に、考え行動し、具体的な成果をつくること」
だと僕は解釈しました。
2010年04月17日
ちょっとHな本(?)

ちょっとHな本かと思わせる表紙ですが、
実は、ピーター・ドラッガーの本です。
AMAZONで売れていて、気になっていたんですが、
同じIKORAブロガーの方が買われていたので、
買いました。
また、中身は、機会があれば紹介したいと思います。
2010年04月15日
第5条 月給の額を忘れよ
愉快に働く10か条
「第5条 月給の額を忘れよ」
月給の額を忘れよ!と言われても、
殆どの人は、生活や楽しみのために、お金を稼ぐために
仕事をしています。
ですから、忘れろって言われても、忘れられるものではないと思います。
もちろん、僕自身も、全くのボランティアで仕事をしていて
100%愉快でいられるかと言うと、自信がありません。
しかし、余談ですが、
僕自身も含めて、中小企業の経営者は、時には
給料を満足に取れないどころか、自分の私財を投じても
会社を守らなければならない時があります。
話を元に戻して
このことに関して
松下幸之助翁は、次のように述べられています。
「給料半分、使命感半分」だと。
つまり、お金のためだけに仕事をすると考えたり、
あるいは、給料に不満があるかといって、全力で仕事をしないという姿勢では
いけないとおっしゃっています。
元来、得られる報酬とは、
自分があげた成果や実績
また、世の中や他人のために、どれぐらい役にたてたかという
対価として、頂ける物であると僕は、思います。
ですから、使命感をもって、全力で仕事に取り組み、その結果として月給を頂く
という、順番で考えるように、僕はしています。
給料が低いのは、自分の働きがあるいからだと、考えています。
月給の額だけを考えて仕事をしていると、必ず不平不満がでてきます。
そうすると、仕事を楽しくできないのは、当然です。
一方で、仕事の目標達成や、自分の能力の向上、よりお客様の満足に応え、誉められる
このようなことに、着目していると、どんどん仕事が楽しくなるはずです。
そして、その結果として、月給を頂き、その範囲内の中で、生活や楽しみを見つける。
こう考えると、楽しく働けるのだと、藤原銀次郎翁は、おっしゃっていると思います。
また、人間のDNAには、人の喜びを自らの喜びとする遺伝子があると
村上和雄さんは、おっしゃっています。
さらに、ホーソン実験では、働く環境や待遇によって、作業効率が変わるものではなく、
自分がどれだけみとめられているのかと言うことや、人間関係などによって、変わるものであると
いう結果がでています。
以上のことからも、人間は、元来自分のお金儲けのためだけに働いて喜べる生き物ではないということがいえると思います。
この考えは、アメリカの成果主義からくるものだと思いますが、その結果、マネーゲームのような経済は崩壊してしまいました。
また、日本人は、元来狩猟民族ではなく、農耕民族で、いろんな人と和をもって協力して、作物をつくり、
分配してきました。
長くなりましたが、
「月給の額を忘れよ」とは
「お金に追われず、仕事の成果を追え!」
ということだと思いました。
「第5条 月給の額を忘れよ」
月給の額を忘れよ!と言われても、
殆どの人は、生活や楽しみのために、お金を稼ぐために
仕事をしています。
ですから、忘れろって言われても、忘れられるものではないと思います。
もちろん、僕自身も、全くのボランティアで仕事をしていて
100%愉快でいられるかと言うと、自信がありません。
しかし、余談ですが、
僕自身も含めて、中小企業の経営者は、時には
給料を満足に取れないどころか、自分の私財を投じても
会社を守らなければならない時があります。
話を元に戻して
このことに関して
松下幸之助翁は、次のように述べられています。
「給料半分、使命感半分」だと。
つまり、お金のためだけに仕事をすると考えたり、
あるいは、給料に不満があるかといって、全力で仕事をしないという姿勢では
いけないとおっしゃっています。
元来、得られる報酬とは、
自分があげた成果や実績
また、世の中や他人のために、どれぐらい役にたてたかという
対価として、頂ける物であると僕は、思います。
ですから、使命感をもって、全力で仕事に取り組み、その結果として月給を頂く
という、順番で考えるように、僕はしています。
給料が低いのは、自分の働きがあるいからだと、考えています。
月給の額だけを考えて仕事をしていると、必ず不平不満がでてきます。
そうすると、仕事を楽しくできないのは、当然です。
一方で、仕事の目標達成や、自分の能力の向上、よりお客様の満足に応え、誉められる
このようなことに、着目していると、どんどん仕事が楽しくなるはずです。
そして、その結果として、月給を頂き、その範囲内の中で、生活や楽しみを見つける。
こう考えると、楽しく働けるのだと、藤原銀次郎翁は、おっしゃっていると思います。
また、人間のDNAには、人の喜びを自らの喜びとする遺伝子があると
村上和雄さんは、おっしゃっています。
さらに、ホーソン実験では、働く環境や待遇によって、作業効率が変わるものではなく、
自分がどれだけみとめられているのかと言うことや、人間関係などによって、変わるものであると
いう結果がでています。
以上のことからも、人間は、元来自分のお金儲けのためだけに働いて喜べる生き物ではないということがいえると思います。
この考えは、アメリカの成果主義からくるものだと思いますが、その結果、マネーゲームのような経済は崩壊してしまいました。
また、日本人は、元来狩猟民族ではなく、農耕民族で、いろんな人と和をもって協力して、作物をつくり、
分配してきました。
長くなりましたが、
「月給の額を忘れよ」とは
「お金に追われず、仕事の成果を追え!」
ということだと思いました。
2010年04月11日
第4条 卒業証書は無いと思え
愉快に働く10か条
「第4条 卒業証書は無いと思え」
偉大なる経営学者であるピーター・ドラッガー博士は、
仕事観に関して以下のように述べておられます。
「仕事は、人生のすべてではない。しかし、仕事が第一である。」
と述べられています。
仕事をするタイプには、次のの3つタイプに分かれると思います。
1、お金をもうけるのみで、給料のいいところに転職を繰り返します。
また、お金という動機で仕事をするタイプ
2、昔からいう、「休まず、働かず」というタイプ。時間通りに出社し、時間通りに退社する。
家では、趣味や余暇の楽しみに高じます。のんびりと人生を過ごしたいタイプ。
3、仕事に対して、意欲を持ち、どちらかと言うと、仕事一辺倒で、仕事で成果を上げ、自己の成長意欲も高く、明確な目標をもって、頑張るタイプ。
1番目と3番目は、
周りとあまり強調せずに、自分ひとりでやろうとするタイプと、
周りの人にも配慮しながら、チームで成果をつくろうとするタイプに分かれます。
また、2番目のタイプは、
一人で黙々と自分の仕事をするタイプと、周りの人と冗談などを言い合って、楽しくのんびりとする
タイプに分かれると思います。
と、いろんな仕事のしかたのタイプの人がいますが、
ある程度、仕事を覚え、自分の仕事のやり方が決まってくると、
殆どの人は、そこで不平不満が出てきます。
仕事自体や、会社の方針、待遇、周りの人の仕事の仕方などに対しての不満です。
これは、目標が低かったり、もうこれで「自分は、なんでもできる」と思ってしまうからです。
要するに、それ以上の成長意欲がなくなった場合です。
不平、不満ばかりを考え始めたり、目標もなく、ただ単に作業としての仕事をしていると
仕事が面白くなくなるのは、当然です。
また、世の中は、変化していきます。
それに対応した仕事をしなければ、自分自身も会社も世間から置いてきぼりにされます。

飲食業界でいうと
牛丼で好調だった
「吉野家」さんは、ゼンショー(すき屋)さん松屋さんとの価格競争に負け、
今期は、赤字に転落しました。
吉野家さんは、2度の危機を乗り越えた立派な会社ですが、
また、赤字転落、他社との終わりなき低価格競争と苦境に立たされています。
これこそが、「仕事には、卒業証書はないと思え」という藤原銀次郎翁の
おっしゃっている意味なのかもしれません。
また、仕事をして、階級があがると、
「それは、新入社員の仕事だ。」とか
「それは、若いものの仕事だ。」といって
下位の方のする仕事を全くしなくなる人が
いますが、
もし、部下の人が困っていたり、
自分が手が空いているなら、手伝ってあげる。
そんなことが、いい人間関係を気づき
明るく楽しい職場になると僕は思います。
つまり、どんな単純な
例えば、昨日のブログで書いた
お茶汲みや鉛筆けづりのような仕事でさえ
卒業証書はないと仰っているのだと
僕は、思いました。
「卒業証書はないと思え!」とは
「一生、勉強である」
と言うことだと僕は解釈をいたしました。
「第4条 卒業証書は無いと思え」
偉大なる経営学者であるピーター・ドラッガー博士は、
仕事観に関して以下のように述べておられます。
「仕事は、人生のすべてではない。しかし、仕事が第一である。」
と述べられています。
仕事をするタイプには、次のの3つタイプに分かれると思います。
1、お金をもうけるのみで、給料のいいところに転職を繰り返します。
また、お金という動機で仕事をするタイプ
2、昔からいう、「休まず、働かず」というタイプ。時間通りに出社し、時間通りに退社する。
家では、趣味や余暇の楽しみに高じます。のんびりと人生を過ごしたいタイプ。
3、仕事に対して、意欲を持ち、どちらかと言うと、仕事一辺倒で、仕事で成果を上げ、自己の成長意欲も高く、明確な目標をもって、頑張るタイプ。
1番目と3番目は、
周りとあまり強調せずに、自分ひとりでやろうとするタイプと、
周りの人にも配慮しながら、チームで成果をつくろうとするタイプに分かれます。
また、2番目のタイプは、
一人で黙々と自分の仕事をするタイプと、周りの人と冗談などを言い合って、楽しくのんびりとする
タイプに分かれると思います。
と、いろんな仕事のしかたのタイプの人がいますが、
ある程度、仕事を覚え、自分の仕事のやり方が決まってくると、
殆どの人は、そこで不平不満が出てきます。
仕事自体や、会社の方針、待遇、周りの人の仕事の仕方などに対しての不満です。
これは、目標が低かったり、もうこれで「自分は、なんでもできる」と思ってしまうからです。
要するに、それ以上の成長意欲がなくなった場合です。
不平、不満ばかりを考え始めたり、目標もなく、ただ単に作業としての仕事をしていると
仕事が面白くなくなるのは、当然です。
また、世の中は、変化していきます。
それに対応した仕事をしなければ、自分自身も会社も世間から置いてきぼりにされます。

飲食業界でいうと
牛丼で好調だった
「吉野家」さんは、ゼンショー(すき屋)さん松屋さんとの価格競争に負け、
今期は、赤字に転落しました。
吉野家さんは、2度の危機を乗り越えた立派な会社ですが、
また、赤字転落、他社との終わりなき低価格競争と苦境に立たされています。
これこそが、「仕事には、卒業証書はないと思え」という藤原銀次郎翁の
おっしゃっている意味なのかもしれません。
また、仕事をして、階級があがると、
「それは、新入社員の仕事だ。」とか
「それは、若いものの仕事だ。」といって
下位の方のする仕事を全くしなくなる人が
いますが、
もし、部下の人が困っていたり、
自分が手が空いているなら、手伝ってあげる。
そんなことが、いい人間関係を気づき
明るく楽しい職場になると僕は思います。
つまり、どんな単純な
例えば、昨日のブログで書いた
お茶汲みや鉛筆けづりのような仕事でさえ
卒業証書はないと仰っているのだと
僕は、思いました。
「卒業証書はないと思え!」とは
「一生、勉強である」
と言うことだと僕は解釈をいたしました。
2010年04月10日
第3条 仕事を自分の趣味にせよ
愉快に働く10か条
「第3条 仕事を自分の趣味にせよ」
趣味が高じて仕事になったというのは、聞く話です。
また、仕事を愉快にするために、お趣味でストレスを発散するというのも
殆どの方が、されていることだと思います。
私もどちらかと言えば、その部類です。
仕事、仕事では、息が詰まります。
と、その考えに問題がると、気がつきました。
趣味というのをYahoo辞書でひくと
とありました。
ここでは、1番目の解釈でしょう。
その中の楽しみとしている
この部分が大切だと気づきました。
愉快に働くためには、
仕事を苦行や生活やお金のために仕方なくしていると考えているうちは、
当たり前ですが、楽しく仕事ができるわけがありません。
つまり、
「楽しみながら、仕事を行いなさい」ということだと思います。
また、趣味のように寝食を忘れて、仕事を行うことで
仕事に面白みが出てくるということかもしれません。
では、趣味と思えるぐらい楽しく仕事をする為には、
どうすればいいのでしょうか?
ここまでで、言うと
第1条 第2条で述べた
自らが進んで、仕事に問いを持ち、一生懸命に取り組むことではないかと思いました。
「第3条 仕事を自分の趣味にせよ」
趣味が高じて仕事になったというのは、聞く話です。
また、仕事を愉快にするために、お趣味でストレスを発散するというのも
殆どの方が、されていることだと思います。
私もどちらかと言えば、その部類です。
仕事、仕事では、息が詰まります。
と、その考えに問題がると、気がつきました。
趣味というのをYahoo辞書でひくと
しゅ‐み【趣味】
「しゅみ」を大辞林でも検索する
1 仕事・職業としてでなく、個人が楽しみとしてしている事柄。「―は読書です」「―と実益を兼ねる」「多―」
2 どういうものに美しさやおもしろさを感じるかという、その人の感覚のあり方。好みの傾向。「―の悪い飾り付け」「少女―」
3 物事のもっている味わい。おもむき。情趣。
とありました。
ここでは、1番目の解釈でしょう。
その中の楽しみとしている
この部分が大切だと気づきました。
愉快に働くためには、
仕事を苦行や生活やお金のために仕方なくしていると考えているうちは、
当たり前ですが、楽しく仕事ができるわけがありません。
つまり、
「楽しみながら、仕事を行いなさい」ということだと思います。
また、趣味のように寝食を忘れて、仕事を行うことで
仕事に面白みが出てくるということかもしれません。
では、趣味と思えるぐらい楽しく仕事をする為には、
どうすればいいのでしょうか?
ここまでで、言うと
第1条 第2条で述べた
自らが進んで、仕事に問いを持ち、一生懸命に取り組むことではないかと思いました。
2010年04月09日
第2条 仕事を自分の学問にせよ
愉快に働く10か条の
「第2条 仕事を自分の学問にせよ」
仕事を通じて、多くの学びがあります。
挨拶や社会人としてのマナーをはじめ
専門的なスキルや知識を身のつけていくことは、もちろん
コミュニケーション能力や、計画をたてて、実行していく能力
など、様々な能力を学び、身につけることも
学問といえるでしょう。
しかし、藤原銀次郎さんの仰る学問とは、もっと奥深いものではないかと思います。
wikipediaによると
学問とは、文化の1つで、系統的・体系的知見の総体である。学問の専門家を一般に「学者」と呼ぶ。
とあります。
とすれば、学者になるぐらい究められるように、仕事に打ち込みなさいということだと
私は、理解しました。
たとえ、それが新入社員さんのうちは、コピー取りやお茶汲みだとしても
その仕事をつまらない仕事、誰でもできる仕事だと思わず、
いかに美味しいお茶をいれるか?
いかにお茶の葉を無駄なく使うか?
いかに早く入れるか?
いかにそのお茶で、飲んだ人の心を和ませ、仕事を捗らせてがることができるか?
などなど、突き詰めると色々な問い(課題)があります。
学問という字を見ると
「問うて学ぶ」とあります。
一つのことでも、様々な疑問(問い)を持ちながら、突き詰め学んでいくことが
「学問」といえるのかもしれません。
優秀なホステスさんは、水割りを作る時に
お客様によって、濃さや作るスピードやタイミングを変えるそうです。
たとえ、社内のお茶でも、
濃い目が好きな人
熱いのが好きな人
たっぷり飲みたい人
色々好みがあるでしょう?
また、来店されたお客様なら
好みが分りませんから
その人の体型や表情から
感情や好みを読み取って
つくるしかありません。
そんな方がいたらそれこそ
「お茶汲みの学者」といえるのでは、ないでしょうか?
「たかがお茶汲みでここまでして、何の役に立つの?」と
思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
「一芸に秀でるものは、万芸に通ず。」と言います。
また、そういう風にお茶を入れる人がいたら、
社内外を問わず、そういう人を登用したくなるはずです。
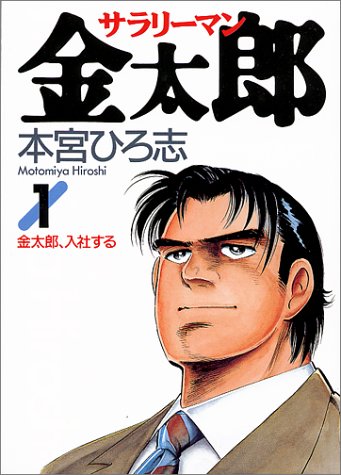
昔、「サラリーマン金太郎」という漫画で、
主人公の矢島金太郎は、暴走族からサラリーマンになった時
鉛筆削りを命じられて、ひたすらそれをしていました。
そうすると、それを使う上司から
「こんなに使いやすい鉛筆を削るのは、誰だ?」
認められて、最終的には、社長まで上り詰めたと言う話が
ありました。
漫画の中の世界ですが、
藤原銀次郎さんの言う
「仕事を学問にせよ」とは、こういうことで
「仕事を、自分の学問になるぐらいに一生懸命に行いなさい」ということだと
僕は、解釈をいたしました。
「第2条 仕事を自分の学問にせよ」
仕事を通じて、多くの学びがあります。
挨拶や社会人としてのマナーをはじめ
専門的なスキルや知識を身のつけていくことは、もちろん
コミュニケーション能力や、計画をたてて、実行していく能力
など、様々な能力を学び、身につけることも
学問といえるでしょう。
しかし、藤原銀次郎さんの仰る学問とは、もっと奥深いものではないかと思います。
wikipediaによると
学問とは、文化の1つで、系統的・体系的知見の総体である。学問の専門家を一般に「学者」と呼ぶ。
とあります。
とすれば、学者になるぐらい究められるように、仕事に打ち込みなさいということだと
私は、理解しました。
たとえ、それが新入社員さんのうちは、コピー取りやお茶汲みだとしても
その仕事をつまらない仕事、誰でもできる仕事だと思わず、
いかに美味しいお茶をいれるか?
いかにお茶の葉を無駄なく使うか?
いかに早く入れるか?
いかにそのお茶で、飲んだ人の心を和ませ、仕事を捗らせてがることができるか?
などなど、突き詰めると色々な問い(課題)があります。
学問という字を見ると
「問うて学ぶ」とあります。
一つのことでも、様々な疑問(問い)を持ちながら、突き詰め学んでいくことが
「学問」といえるのかもしれません。
優秀なホステスさんは、水割りを作る時に
お客様によって、濃さや作るスピードやタイミングを変えるそうです。
たとえ、社内のお茶でも、
濃い目が好きな人
熱いのが好きな人
たっぷり飲みたい人
色々好みがあるでしょう?
また、来店されたお客様なら
好みが分りませんから
その人の体型や表情から
感情や好みを読み取って
つくるしかありません。
そんな方がいたらそれこそ
「お茶汲みの学者」といえるのでは、ないでしょうか?
「たかがお茶汲みでここまでして、何の役に立つの?」と
思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
「一芸に秀でるものは、万芸に通ず。」と言います。
また、そういう風にお茶を入れる人がいたら、
社内外を問わず、そういう人を登用したくなるはずです。
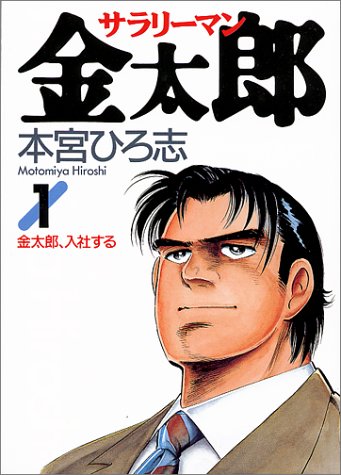
昔、「サラリーマン金太郎」という漫画で、
主人公の矢島金太郎は、暴走族からサラリーマンになった時
鉛筆削りを命じられて、ひたすらそれをしていました。
そうすると、それを使う上司から
「こんなに使いやすい鉛筆を削るのは、誰だ?」
認められて、最終的には、社長まで上り詰めたと言う話が
ありました。
漫画の中の世界ですが、
藤原銀次郎さんの言う
「仕事を学問にせよ」とは、こういうことで
「仕事を、自分の学問になるぐらいに一生懸命に行いなさい」ということだと
僕は、解釈をいたしました。
2010年04月08日
第1条 仕事を自分のものにする
愉快に働く10か条
「第1条 仕事を自分のものにする」
愉快に楽しく仕事をするためには、どうすればいいのか?
この問いに対する僕の答えは、
「愉快に楽しく仕事をする為には、どうすればいいのか?」
ということを考えればいいのです。
これは、別にふざけているわけでは、ありません。
あるいは
「愉快に楽しく仕事をしよう」と決めればいいのです。
どういうことかと言うと、
拝金主義の現代では、
どうすれば、楽してお金儲けができるのか?
生活やお金のために仕事をする。
だから、仕事とは辛くて、しんどいものだから仕方ない。
だから、我慢して、できるだけ楽をしてお金をかせごうと考えるのです。
しかし、こういう仕事の仕方をしていると
会社では、指示待ちの仕事しかできなくなります。
創意工夫がないので、単純作業の繰り返しになります。
そうすると、当然会社では、干されたり、単純な仕事、簡単な仕事しか与えてもらえなくなります。
アルバイトさんなら、シフトを減らされ、短時間でしか働けなくなるでしょう。
結果的に昇給、昇進はなし。アルバイトさんも短時間になるので、結果的に収入がへることになります。
また、顧客のニーズは、めまぐるしく変化し多様化していますから、
何の創意工夫もしない社員ばかりで構成されている会社は、業績があがりません。
結果的に、また昇給などは望めないばかりか、逆に減給やリストラの対象となります。
「仕事を自分のものにする」とは
仕事を習得するという意味もあるかもしれませんが、
会社や職場の仕事は、全部自分の仕事であるというぐらいの気概で
「全ての仕事は、自分のすべきものだ」というぐらいがいいのでは、ないかと思います。
人から仕事を教えてもらったり、指示されてから動くのではなく、
自分で仕事をみつけ、どんどんやっていく。
他の人のやっている仕事を助けるのもよし、新たな事をはじめるのもよし。
新入社員の方で、まだその仕事のスキルがない方は、掃除をされるのがいいのではないかと思います。
僕は、トイレ掃除をして
「業者をやとっているのだから、大学まで出て、そんなことせんでいい。」と怒られましたが、
徹底的に、一生懸命にやりましたので、
周りのスタッフには、匂いがなくなった。きれいになったと喜ばれました。
それもまたいい経験となりました。
仕事を見つけるには、新しい仕事を見つける方法と、
今やっている仕事をより深くするという方法があります。
仕事の時間は、限られた時間しかありませんから、新しい仕事をしようとすると
どうすれば、もっと早く効率よくできるだろうと、考え、工夫します。
そうすることで、仕事の能力が高くなり、また会社の生産性があがり、
業績があがります。
その結果、給料やボーナスに反映されてきます。
また、指示待ちで、人から言われた仕事には、不平不満、愚痴がつきものですが
自らが選択してした仕事には、それらは生まれません。
また、人から言われた仕事では、あまり気持ちがはいりません。ややもすれば
適当にしておこうとさえ思うときがあります。
しかし、自分でやろうと思った仕事は、一生懸命にやります。
「仕事を自分のものにする」とは
「仕事を自ら進んで行う」
ということだと僕は思います。
「第1条 仕事を自分のものにする」
愉快に楽しく仕事をするためには、どうすればいいのか?
この問いに対する僕の答えは、
「愉快に楽しく仕事をする為には、どうすればいいのか?」
ということを考えればいいのです。
これは、別にふざけているわけでは、ありません。
あるいは
「愉快に楽しく仕事をしよう」と決めればいいのです。
どういうことかと言うと、
拝金主義の現代では、
どうすれば、楽してお金儲けができるのか?
生活やお金のために仕事をする。
だから、仕事とは辛くて、しんどいものだから仕方ない。
だから、我慢して、できるだけ楽をしてお金をかせごうと考えるのです。
しかし、こういう仕事の仕方をしていると
会社では、指示待ちの仕事しかできなくなります。
創意工夫がないので、単純作業の繰り返しになります。
そうすると、当然会社では、干されたり、単純な仕事、簡単な仕事しか与えてもらえなくなります。
アルバイトさんなら、シフトを減らされ、短時間でしか働けなくなるでしょう。
結果的に昇給、昇進はなし。アルバイトさんも短時間になるので、結果的に収入がへることになります。
また、顧客のニーズは、めまぐるしく変化し多様化していますから、
何の創意工夫もしない社員ばかりで構成されている会社は、業績があがりません。
結果的に、また昇給などは望めないばかりか、逆に減給やリストラの対象となります。
「仕事を自分のものにする」とは
仕事を習得するという意味もあるかもしれませんが、
会社や職場の仕事は、全部自分の仕事であるというぐらいの気概で
「全ての仕事は、自分のすべきものだ」というぐらいがいいのでは、ないかと思います。
人から仕事を教えてもらったり、指示されてから動くのではなく、
自分で仕事をみつけ、どんどんやっていく。
他の人のやっている仕事を助けるのもよし、新たな事をはじめるのもよし。
新入社員の方で、まだその仕事のスキルがない方は、掃除をされるのがいいのではないかと思います。
僕は、トイレ掃除をして
「業者をやとっているのだから、大学まで出て、そんなことせんでいい。」と怒られましたが、
徹底的に、一生懸命にやりましたので、
周りのスタッフには、匂いがなくなった。きれいになったと喜ばれました。
それもまたいい経験となりました。
仕事を見つけるには、新しい仕事を見つける方法と、
今やっている仕事をより深くするという方法があります。
仕事の時間は、限られた時間しかありませんから、新しい仕事をしようとすると
どうすれば、もっと早く効率よくできるだろうと、考え、工夫します。
そうすることで、仕事の能力が高くなり、また会社の生産性があがり、
業績があがります。
その結果、給料やボーナスに反映されてきます。
また、指示待ちで、人から言われた仕事には、不平不満、愚痴がつきものですが
自らが選択してした仕事には、それらは生まれません。
また、人から言われた仕事では、あまり気持ちがはいりません。ややもすれば
適当にしておこうとさえ思うときがあります。
しかし、自分でやろうと思った仕事は、一生懸命にやります。
「仕事を自分のものにする」とは
「仕事を自ら進んで行う」
ということだと僕は思います。
2010年04月07日
愉快に働く10か条
新入社員さんが仕事はじめると
「こんなはずではなかった。」
「仕事が面白くない。つまらない。」
「なんのために仕事をするのか?」
と悩み始めることは、しばしばあります。
そこで、今回は、
「製紙王」とよばれた藤原銀次郎さんの
愉快に働く10か条を紹介します。
第1条 仕事を自分のものにせよ
第2条 仕事を自分の学問にせよ
第3条 仕事を自分の趣味にせよ
第4条 卒業証書は無いと思え
第5条 月給の額を忘れよ
第6条 仕事に使はれて人に使はれるな
第7条 時々必ず大息を抜け
第8条 先輩の言行に学べ
第9条 新しい発明発見に努めよ
第10条 仕事の報酬は仕事である
それぞれの内容については、改めて少しづつ紹介したいと思います。
「こんなはずではなかった。」
「仕事が面白くない。つまらない。」
「なんのために仕事をするのか?」
と悩み始めることは、しばしばあります。
そこで、今回は、
「製紙王」とよばれた藤原銀次郎さんの
愉快に働く10か条を紹介します。
第1条 仕事を自分のものにせよ
第2条 仕事を自分の学問にせよ
第3条 仕事を自分の趣味にせよ
第4条 卒業証書は無いと思え
第5条 月給の額を忘れよ
第6条 仕事に使はれて人に使はれるな
第7条 時々必ず大息を抜け
第8条 先輩の言行に学べ
第9条 新しい発明発見に努めよ
第10条 仕事の報酬は仕事である
それぞれの内容については、改めて少しづつ紹介したいと思います。
2010年03月20日
ハイパフォーマー
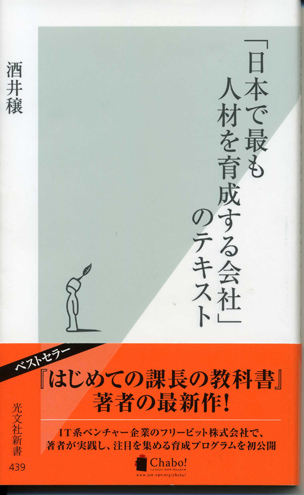
朝の記事では、いわゆる芸術やダンスなどの
意味でパフォーマンスと言う言葉を使いましたが、
今回は、もう一つの意味である、性能や能力と言う意味での
パフォーマンスについて、
「日本で最も人材育成する会社」と言う本より
抜粋、私なりのまとめをして、書きます。
つまり、タイトルの「ハイパフォーマー」とは
いわゆる「仕事の出来る人」と言う意味です。
落合博満元選手やイチロー選手を育てた伝説の
打撃コーチ 故高畠導宏氏は
「伸びる人材の共通点」として
次の7項目を示されています。
1、素直であること
2、好奇心旺盛であること
3、忍耐力があり、あきらめないこと
4、準備を怠らないこと
5、几帳面であること
6、気配りができること
7、夢を持ち、目標を高く、設定することができること
この本の著者 坂井穣さんは、以下のような項目で
伸びる人材かどうかを見極めろとおっしゃています。
1、顧客思考ができるかどうか
他部門や上司や部下、取引先など
自分以外を全て顧客と考えると
「利他」の精神をもっているかどうかということである。
2、見本となる人を持っている。
3、明るく社交的であること
4、失敗は、自分のせいで、成功は運のお陰と考える。
5、「人の見る目」を持ち、他者の力を活用すること。
6、問題意識をもち、自分で調べることができる人。
7、他人にツッコミをいれらる能力があること
完璧人間ではなく、「他人が笑ってゆるしてくれる弱点」をもつことで
周囲からも愛されることという意味です。
8、孤独に耐えられること。
以上です。
これを一言でまとめるなら
他人から好かれる人間であるということだと理解しました。
逆に言えば、
上記の条件は
他人から好かれる条件でもあるということです。
そういう意味においては、
周りの人の評価というものを
人を見極める際には、非常に重要であるということです。
どれだけ、仕事ができていても
どれだけ、成功していたとしても
「他人から好かれていない人」は
長続きしないということかもしれません。
そして、最後にこれらの条件を揃えるように努力するためには、
先の打撃コーチの7つの項目の7番目にあるように
「自分の心を燃やせるような目標や夢」を持つことが
その根底になければならず、
そして、熱い想いをもった目標や夢があるからこそ
前向きな思考、プラス思考、可能思考を生みます。
そうすることによって、自分を成長させていけるのです。
整理すると
夢や目標を掲げる
↓
プラス思考、前向き
↓
誰からも好かれるような人間になるよう努力する。
今日、明日は、忙しくなりそうです。
夢、目標を達成するために
今日も頑張ります。