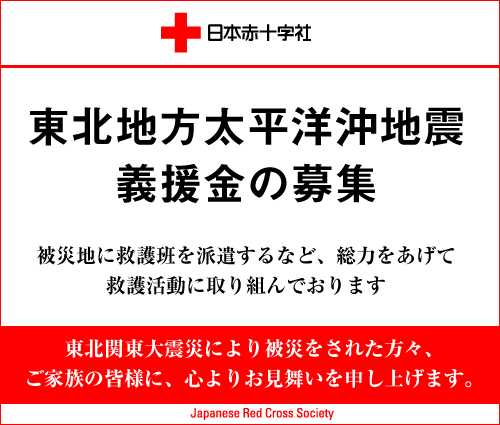2010年08月08日
ありがとうございます。
いつも、ご来店頂いている
先輩経営者のジースリーさんとめがね店の山下さん
に、本日のおすすめ
おこぜとこちのお造りをお召し上がり頂きました。

「ふぐに似た感じで美味しい」と言って頂きました。
感謝!!
先輩経営者のジースリーさんとめがね店の山下さん
に、本日のおすすめ
おこぜとこちのお造りをお召し上がり頂きました。

「ふぐに似た感じで美味しい」と言って頂きました。
感謝!!
2010年08月08日
美味しい魚には毒がある?!
今日は、通常の仕入以外に、勉強のために変わった魚を仕入れました。
背びれに猛毒があるオコゼ

押しつぶされたような平たい体と大きなひれをもつコチ

僕は初めて触る魚ですが、
どちらの魚もキッチンのI君は、
手馴れた手つきで捌きます。
オコゼは、毒をもった背びれ以外は
全部食べられるそうです。
コチは、薄造りにして、ポンズで食べても
皮を引かずに、炙り造りにしてもおいしいという
I君の解説付きで、見事に捌かれました。
背びれに猛毒があるオコゼ

押しつぶされたような平たい体と大きなひれをもつコチ

僕は初めて触る魚ですが、
どちらの魚もキッチンのI君は、
手馴れた手つきで捌きます。
オコゼは、毒をもった背びれ以外は
全部食べられるそうです。
コチは、薄造りにして、ポンズで食べても
皮を引かずに、炙り造りにしてもおいしいという
I君の解説付きで、見事に捌かれました。
2010年08月08日
不況知らずのお店
千代田キャピタルマネジメントという会社から送られてくるニュースレターにあった記事を3つ紹介します。
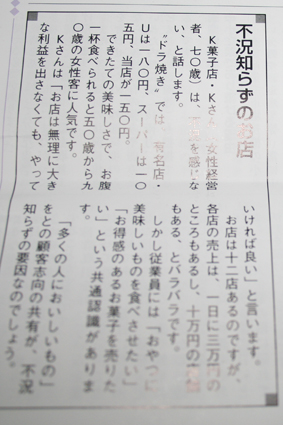
と書いてありました。
僕は、この記事の題名
「不況知らずのお店」というテーマについて
二つの要因があると感じました。
ひとつは、この記事の締めくくりにもあるように
「多くの人においしいもの」という経営理念の浸透です。
経営理念の大切さは、色んな経営の本に書かれています。
そして、もうひとつのここでは、要因として挙げられていなかった
ことは、
「お店は無理に大きな利益を出さなくても、やっていければ良い」
という経営戦略です。
もし、この経営者が
「もっと利益を大きくしたい」
「店舗数を増やしたい」
という拡大戦略をとっていたとしたら
好景気の時は、売上や利益はどんどん伸びていたかもしれません。
しかし、そうでない時は、逆に売上や利益や店舗数は減っていったでしょう。
そうなれば、不況を感じずにはいられなかったでしょう。
自分の会社やお店の売上の落とし所(目標)を
敢えて、低くしているのです。
そうすることにより、
必然的に固定費や負債の額は少なくてすみます
小さな経営に徹しているのです。
決算書を見ていないので、推測ですが
この会社の
損益分岐点比率は、低いと思います。
(安全余裕率は、高いと思います。)
簡単な例でいうと
ラーメン屋さんで
「うちのお店は、どんなにお客様が来ても、30食しか売りません」
というお店が、毎日必ず30人のお客様が来られるとしたら、
そこの売上は、毎日同じ売上で同じ経費です。
しかし、通常の営業スタイルで
お客様が来るだけ売るとか
店舗を増やすことで、在庫や人員や固定費の増大に繋がります。
お客様が右肩上がりで来る間は、いいですが
そうでない場合は、縮小せざるを得ません。
どういう戦略をとるかは、そこのお店や会社によりますが、
K洋菓子店は拡大戦略を取らなかったために
「不況知らず」とK社長が言う
もう一つの要因だと感じました。
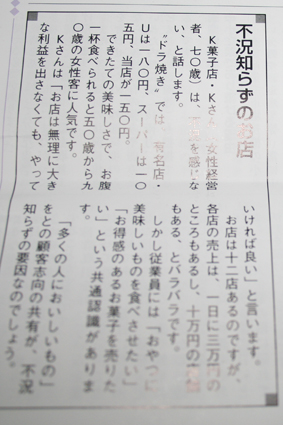
K菓子店・Kさん(女性経営者、70歳)は、
「不況を感じない」と話します。
"ドラ焼"では、有名店・Uは180円、スーパーは105円
そして、K菓子店さんは、150円。
出来たての美味しさで、お腹一杯食べられると50歳から90歳の女性に人気です。
Kさんは、
「お店は無理に大きな利益を出さなくても、やっていなければ良い」と言います。
お店は、十二店あるのですが、各店の売上は、1日3万の所もあるし、
10万円の店舗もあると、バラバラです。
しかし、従業員には「お得感のあるお菓子を売りたい」という
共通認識があります。
「多くの人においしいもの」をとの顧客志向の共有が、不況知らずの要因なのでしょう。
と書いてありました。
僕は、この記事の題名
「不況知らずのお店」というテーマについて
二つの要因があると感じました。
ひとつは、この記事の締めくくりにもあるように
「多くの人においしいもの」という経営理念の浸透です。
経営理念の大切さは、色んな経営の本に書かれています。
そして、もうひとつのここでは、要因として挙げられていなかった
ことは、
「お店は無理に大きな利益を出さなくても、やっていければ良い」
という経営戦略です。
もし、この経営者が
「もっと利益を大きくしたい」
「店舗数を増やしたい」
という拡大戦略をとっていたとしたら
好景気の時は、売上や利益はどんどん伸びていたかもしれません。
しかし、そうでない時は、逆に売上や利益や店舗数は減っていったでしょう。
そうなれば、不況を感じずにはいられなかったでしょう。
自分の会社やお店の売上の落とし所(目標)を
敢えて、低くしているのです。
そうすることにより、
必然的に固定費や負債の額は少なくてすみます
小さな経営に徹しているのです。
決算書を見ていないので、推測ですが
この会社の
損益分岐点比率は、低いと思います。
(安全余裕率は、高いと思います。)
簡単な例でいうと
ラーメン屋さんで
「うちのお店は、どんなにお客様が来ても、30食しか売りません」
というお店が、毎日必ず30人のお客様が来られるとしたら、
そこの売上は、毎日同じ売上で同じ経費です。
しかし、通常の営業スタイルで
お客様が来るだけ売るとか
店舗を増やすことで、在庫や人員や固定費の増大に繋がります。
お客様が右肩上がりで来る間は、いいですが
そうでない場合は、縮小せざるを得ません。
どういう戦略をとるかは、そこのお店や会社によりますが、
K洋菓子店は拡大戦略を取らなかったために
「不況知らず」とK社長が言う
もう一つの要因だと感じました。