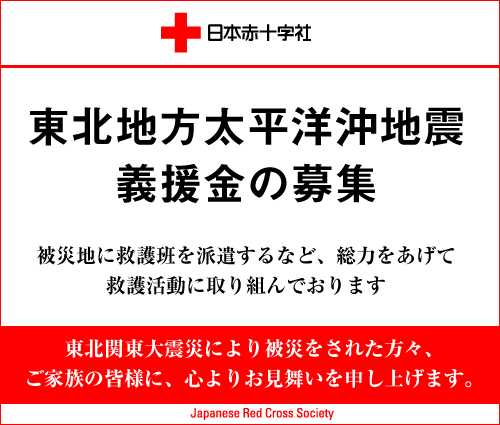2007年10月02日
捨欲即大欲
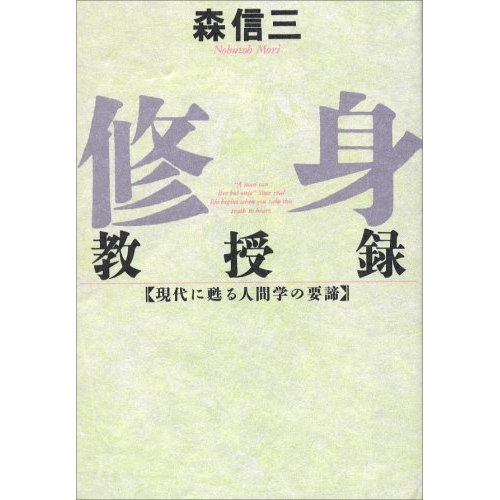
修身教授録―現代に甦る人間学の要諦 (致知選書)
先日のブログでどうも、もやもやしていたことがあって
それは、
欲があるからこそ、人は、目標を持ち、成長するし、困難にも立ち向かっていける。
つまり、欲を捨てるということは、悪いことなのか?
では、ナイチンゲールは、自分の欲を捨てたけれども、大成をなし、世の中に貢献をされた。
とか、いろいろ考えていました。
僕は、去年より、いつも本を持ち歩き、喫茶店やレストランで注文を待っているときや、
銀行で待っているときなどに、少し本を開きます。
そうすると、昨日と今日の2日間で、森信三さんの「修身教授録」という言葉がとても、気になりました。
そして、あまりにも気になるので、家に帰り、本棚からこの「修身教授録」を開いてみると、
パッと開いたページが、第12講の「捨欲即大欲」のページでした。
そして、以前読んだときに、アンダーラインを引いていた言葉が下記です。
人間が真に欲を捨てるということは、実は自己を打ち超えた大欲の立場にたつということです。すなわち自分一身の欲を満足させるのではなくて、天下の人々の欲を思いやり、できることなら、その人々の欲をも満たしてやろうということであります。
とありました。
多分、一度二度この本を読んだ私にはこの森信三さんが真に言われたいことを理解出来ないとは思いますが、私は以下のように解釈しました。
自分の欲を捨てたときに、初めて自分が何のためにこの世に生まれ、何をすべきかということを考えられるようになる。
自分の欲を表に現しているうちは、本当に自分がしたいこと、すべきことは見つからないと。
前にも書いたかもしれませんが、最近は、何か悩んでいて、本を開くと、パッとそのページが開くのです。
なんとも、不思議なことがあるものです。
みなさんは、この「捨欲即大欲」をどのように解釈されますか?
2007年09月21日
積小為大
大事をなさむと欲せば、
小なる事を、
怠らず勤むべし。
小積もりて大となればなり。
およそ小人の常、大なることを欲して、
小なることを怠り、
出来難き事を憂いて、
出来易く事を勤めず。
それゆえ終に大なる事をなすことを能わず。
それ大は小の積んで、
大となる事を知らぬ故なり。
二宮尊徳さんの言葉ですが、
月刊「致知」を開くと、ぱっとこの言葉が書いてありました。
昔、この言葉に出会った時にすごい衝撃的でした。
それまでの僕の生き方は、「いつかは、BIGになったる」と
夢ばかりみて、
「俺はこんな仕事をするような人間じゃない」と考え、
今与えられている仕事をいい加減にこなし、愚痴や不平不満ばかりを言い
まさにこの二宮尊徳さんの言葉の小人の生き方でした。
その言葉がきっかけの一つになり、私は、今与えられたことを精一杯やろう
今この瞬間に全力投球しよう!と誓ったのでした。
未来は現在の道からしかつながっていない
だから、今日も明るい明日にするために、今この瞬間を大切に精一杯生きよう!
自分の将来に憂いがあることあります。
こんなことを毎日続けていたら、この先自分の将来はどうなるのだろうか?
と迷うこともあります。
だからと言って、今の仕事や与えられた環境に不満を持たずに
そういう環境を与えられていることに感謝して、精一杯やってみよう!
Do Your Best! Yes、I Can!といつも自分に言い聞かせながら、
頑張っています。
まずは、目の前のごみを拾うことから、はじめようっと・・・・
小なる事を、
怠らず勤むべし。
小積もりて大となればなり。
およそ小人の常、大なることを欲して、
小なることを怠り、
出来難き事を憂いて、
出来易く事を勤めず。
それゆえ終に大なる事をなすことを能わず。
それ大は小の積んで、
大となる事を知らぬ故なり。
二宮尊徳さんの言葉ですが、
月刊「致知」を開くと、ぱっとこの言葉が書いてありました。
昔、この言葉に出会った時にすごい衝撃的でした。
それまでの僕の生き方は、「いつかは、BIGになったる」と
夢ばかりみて、
「俺はこんな仕事をするような人間じゃない」と考え、
今与えられている仕事をいい加減にこなし、愚痴や不平不満ばかりを言い
まさにこの二宮尊徳さんの言葉の小人の生き方でした。
その言葉がきっかけの一つになり、私は、今与えられたことを精一杯やろう
今この瞬間に全力投球しよう!と誓ったのでした。
未来は現在の道からしかつながっていない
だから、今日も明るい明日にするために、今この瞬間を大切に精一杯生きよう!
自分の将来に憂いがあることあります。
こんなことを毎日続けていたら、この先自分の将来はどうなるのだろうか?
と迷うこともあります。
だからと言って、今の仕事や与えられた環境に不満を持たずに
そういう環境を与えられていることに感謝して、精一杯やってみよう!
Do Your Best! Yes、I Can!といつも自分に言い聞かせながら、
頑張っています。
まずは、目の前のごみを拾うことから、はじめようっと・・・・

2007年08月20日
真実の自己とは何か
「生きるとは」のスイカさんのコメントを受けて
以下は、芳村思風先生の『人間の格』という本の第2章を私なりに要約したものです。
【どんこい流の要約 終わり】
あくまで私なりの解釈ですので、詳しい内容、正しい理解は、本を読まれるか、芳村先生の講演をお聞きください。
以下は、芳村思風先生の『人間の格』という本の第2章を私なりに要約したものです。
人生の目的というものをどのように見つけ出せば、本当の自分の人生の充実感に結びつくものになるのか?
人生の目的や志は真実の自己との発見と関係します。
そこで、まず、真実の自己とは何かを見つけなければなりません。
人間は生きていく中で変化し成長する存在です。これを理性という能力によって把握することはできません。理性が把握できるものは、一定の秩序や法則の元に変化するものしか把握できません。また、把握するということは、全てを画一的に変化させることしかできません。それがどんなに複雑であっても法則を見つけて分類、体系化するのが理性です。
つまり、それぞれ個性をもち変化していく人間を把握するというのは感性や直感によってしか掴むことができないのです。
そこで感性論哲学では、「呼び出し法」というのを使って真実の自己を発見していきます。「呼び出し法」とは問いかけてでてきたものをつかむという方法です。
これを使って、①「創っていく自分」「創られていく自分」「潜在する自分」という三つの観点から真実の自己を見つけていきます。
「創っていく自分」というのは「どんな人間になりたいか」という問いに対する欲求です。自分はこうなりたいという欲求を呼び覚ますことです。
次に「どんな仕事をしたいのか」という問いに対する欲求を呼び覚ますことです。どんな仕事がしたいのかを考える上で、「潜在する自分」つまり自分にどういう能力があるのかということをはっきり知ることです。
それを知る手がかりとしてやってみたら、
①好きになる所
②興味や関心が沸いてくる所
③得意と思える所
④他人と比べてよくできる所
⑤問題意識が沸いてくる所で頑張る。
この五つが自分に与えられて天分を発見する方法です。
そして、「将来どういう生活がしたいのか」を問いに対する欲求を呼び覚ますことです。
それらにより、人間として基本的な目標、社会的な存在として持っていなければならない目標、将来の人生の目標という三つの観点からの自分に対しての問いかけをして、自分の中に眠っている欲求を呼び覚ますことが大事です。
次は二番目の「創られていく自分」という観点から人生の目的を発見する方法です。
創られた自分とは、人間は人生の出会いによって、創られていくという側面があるということです。出会いによって創られていくものは性格と長所と短所です。
そしてこの三つの中で、実現する価値のある自分を創っていくには長所を伸ばすことです。
長所を伸ばして存在感のある自己をつくる、個性をつくる。その伸ばす努力により、短所は人間の味に変わり、また短所を自覚することにより、秀でた長所をもちながらも謙虚な気持ちで生きていくことができます。
また、教育もまた同じように、長所を見つけ、伸ばしてあげることがその人を輝かせ、人を生かすことになります。
三番目の真実の自己の発見方法は、潜在能力という観点からどう発見するかという方法です。
それは、現実と深く関わることによって、「どうも、おかしいな」とか「どうも、納得できない」というような現実への異和感という感性の実感から、真実の自己を発見することができます。
この現実への異和感という感性の実感を感じ取ることができた人間ならば、必ずなんとかできる能力を持っていることを教えてくれている。つまり、自分の潜在能力に対応した形で問題意識がでてきます。さらにその潜在能力を引き出すには、現在自分のもっている力を全て出し切り、それでもその問題を解決していきたいという欲求からあきらめずに努力することで、潜在能力が顕在化してきます。
以上、自分の意志に基づいてつくってゆく自分、人生の出会いに基づいて創られていく自分、現実の異和感として出てくる現在の自分という、三つの方法で実現する価値のある本当の自分を発見できます。
【どんこい流の要約 終わり】
あくまで私なりの解釈ですので、詳しい内容、正しい理解は、本を読まれるか、芳村先生の講演をお聞きください。
2007年08月19日
生きるとは・・・
山田淳二さんのブログを受けて、
生きていると、死にたいと思うときは、誰しもあると思います。
私も、何度もあります。
女に振られたとき。仕事で失敗した時。お金に困ったとき。孤独感を感じてどうしようもなく、寂しい気持ちになった時。・・・・etc
しかし、その最後の選択をどちらを選ぶかは、自分の命の意味について、考えたことがあるかどうかでは、ないでしょうか?
どんな人生を歩んでも、必ず、イバラの道もあるはずです。
しかし、それは、その人にとって、乗り越えられる障害や問題しか起きないと言われています。
すべて、自分の命の意味を全うしていくための、成長への試練だと。
でも、その試練に敗れても打ち勝っても、どっちでもいいと思います。
大切なことは、そこにチャレンジするかどうかだけだと。
私はそう信じます。
芳村思風さんは、以下のように述べていられます。
日本の良さは、本来「利」を追い求めて、競争する文化ではなく、「仁」を持って、共に助け合い、力を合わせて、成り立ってきた文化であると、思います。
元来の狩猟民族と農耕民族の違いからでしょうか?
だからこそ、互いに思いやり、力を合わせて、地域や社会をよくしていくために、仕事をする。
その結果としての「利」を得ていくのが、日本人の姿では、ないでしょうか?
だから、このブログもみんなで力を合わせて、和歌山のいいところをもっともっとアピールして
いい街ができたら、素晴らしいなぁって思います。
【なんの根拠もない、どんこいの一人言でした】
生きていると、死にたいと思うときは、誰しもあると思います。
私も、何度もあります。
女に振られたとき。仕事で失敗した時。お金に困ったとき。孤独感を感じてどうしようもなく、寂しい気持ちになった時。・・・・etc
しかし、その最後の選択をどちらを選ぶかは、自分の命の意味について、考えたことがあるかどうかでは、ないでしょうか?
どんな人生を歩んでも、必ず、イバラの道もあるはずです。
しかし、それは、その人にとって、乗り越えられる障害や問題しか起きないと言われています。
すべて、自分の命の意味を全うしていくための、成長への試練だと。
でも、その試練に敗れても打ち勝っても、どっちでもいいと思います。
大切なことは、そこにチャレンジするかどうかだけだと。
私はそう信じます。
芳村思風さんは、以下のように述べていられます。
●実現するべき自己の発見
人間において生きるとは、ただ単に生き永らえることではない。
人間において生きるとは、
「何の為にこの命を使うか」、「この命をどう生かすか」ということである。
命を生かすとは、何かに命をかけるということである。
だから、生きるとは、命をかけるということだ。
命の最高の喜びは、
命をかけても惜しく無い程の対象と出会うことにある。
その時こそ、命は最も充実した生の喜びを味わい、
激しくも、美しく燃え上がるのである。
君は、何に命をかけるか。
君は、何の為になら死ぬことが出来るか。
この問いに答えることが、生きるということであり、
この問いに答えることが、人生である。
●助け合って生きるための学問
誰も、この苦しみを、気持ちを、わかってくれない。
誰も俺の事を本当にはわかってくれない。
この思いは、誰の胸にも、死ぬまで付きまとうものである。
人間は、本質的に、根元的に、
誰でも、皆、さみしいのである。孤独なのである。
しかし、また、人間は、
この誰にも理解されない心を抱えて
人と共に生きて行かなければならない存在である。
そこで、人間は、人と共に生きる為に
人に語りかけ、話し合い、理解し合えるように努力するのである。
いや、努力しなければならないのである。
なぜなら、みんな同じ人間であるからだ。
この、孤独である人間が互いに理解し合おうとし、
その為に、全人類に共通する真実を求め、
それを手がかりに助け合って生きようとする努力、
これこそが他ならぬ哲学なのである。
主義主張で対立する事が哲学なのではない。
日本の良さは、本来「利」を追い求めて、競争する文化ではなく、「仁」を持って、共に助け合い、力を合わせて、成り立ってきた文化であると、思います。
元来の狩猟民族と農耕民族の違いからでしょうか?
だからこそ、互いに思いやり、力を合わせて、地域や社会をよくしていくために、仕事をする。
その結果としての「利」を得ていくのが、日本人の姿では、ないでしょうか?
だから、このブログもみんなで力を合わせて、和歌山のいいところをもっともっとアピールして
いい街ができたら、素晴らしいなぁって思います。
【なんの根拠もない、どんこいの一人言でした】